電波探知機(逆探)【付】電波妨害機
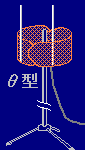
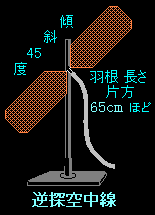

カラーエナメル仕上げは電波兵器中唯一!
◆逆探
海軍で電波探知機(逆探)と呼称していたのは送信機を持たず、敵レーダーから捕捉されるまえに敵の電波を探知する目的の、単なる電波受信装置。つまり、定義上レーダーではない。
まず無指向性アンテナで周波数を変えながら捜索する。
敵レーダーの発射パルス音が聞えたら方向性アンテナに切替えて方位を知る。距離は測定できない。
レーダーは目標物体で反射して弱くなり、更に往復した微弱な電波を受信するが、逆探は片道伝播で電界が強いので敵に知られる前に知れるはず。
初期には受信機内部から局発などの高周波が漏れ、アンテナから逆送して敵に探知される危険があった。その対策と、併せて取扱いを簡易化する改良が重ねられた。
∵3極管の高周波増幅は逆方向に漏れる、それを何とかする工夫!【VHF帯の上半部以上に使える遮蔽格子管は未開発】
| Q&A | 掲示板から転載 |
|---|---|
| Q TH殿 |
逆探のページで受信機からも電波が漏れているとありましたがこれは無線電信機でも起きていたのでしょうか? |
| A |
無線通信ではレーダーより周波数が低いため技術完成度が高く受信機からの電波漏れはありません。 |
【抜いたり挿したりのバンド切り替え方式が、単一バンドに改良されて不便が解消された。】
真空管はエーコン管3個とUZ-6C6が9個
いま思い返して見るにこの装置は簡単ながら、使いこなすには訓練が必要。 「周期的に入感する場合は、まだサーチの段階で、敵はこちらを捕捉していない。連続入感したら発見されたと知れ」とは教えられたが、私がこれで敵と断定できる電波を受信したことがない。電探に比べて方向性が鈍くまた、視覚を使わずに聴覚だけなので、感じた電波が敵のものか友軍のものか判別が難しい。 訓練が必要。
音色が違うかも知れないがテープレコーダーのなかった時代、
声色で「チ〜〜」だとか「ジャージャー」だとか聞かされても
敵の電波を1度体験するまで自信がもてなかっただろう!
敵信分析判断などの訓練は別の兵科で専門にやっていたかと思う。
我等の逆探教育はそれには触れず故障修理のカリキュラムだった。
周波数はダイヤルの2か所で同じ電波が入感する。ヘテロダインの上と下だが大抵は感度に差がない。下側で読み取ることになっていた。
逆探改良
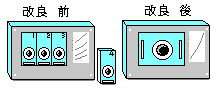 Topの写真も含めて多く配置された型では
Topの写真も含めて多く配置された型では
75MHz〜400MHzが5個のプラグイン部分に分割配分されていて、受け口は3個まで同時に差し込めるようになっていた。つまり2個はいつもあぶれていたわけ 選択用に3段の切替器があった。それぞれについているダイヤルを端から端まで回して切り替え、3個目が終わったら、どれかひとつを引き抜いてあぶれていたユニットに交換する。(アンテナも付け替える)このように全バンドサーチは厄介だった。
3個分のスペースに、大きくて1個で丁度になる型に替わった。前よりも大きいダイヤルが1個、使いやすさと共に、カッコウもいいものになった。プラグイン部分だけで本体は前のものをそのまま使う。改番号は忘れた。
中身は 集中定数回路 から 分布・集中定数併用回路
になった。(s20.3)

右の図の広帯域「ラケット型アンテナ」を輪状に曲げて無指向性アンテナとして使われた。「θ型アンテナ」と呼んだ。
400MHzが上限なので、敵電探がデシ波・サンチ波に移行するにしたがって無用化が進んだ。
戦後刊行の出版物の潜水艦の写真を見ると、上図「ラケット型アンテナ」は平面でなく立体化されている。1回り大きい反射器を取り付けて、単一指向性にしたもののよう。
教わった所では、一般艦船では背後を構造物が遮蔽するため、単一指向性にしても効果が薄く「反射器を外して軽く使った方が有効」の達しがあった、と聞いていた。
その後再検討されたのだろう。潜水艦用は top にも装備する必要からに違いない!
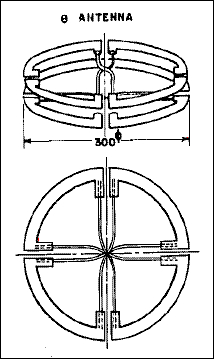 現役の時には、右図のようなアンテナの存在を知らなかった。
現役の時には、右図のようなアンテナの存在を知らなかった。
そして、θ型アンテナと言いば上に述べた物のことを言った。
新型製品は前線投入が先で教育用は後回しになったのだろう。
見たことはないが、近年解放の資料からそのアンテナの
考察を試みる。
θ型無指向性広帯域アンテナの考察
(1) 無指向性(±高角も含む)
(2) 超広帯域(3オクターブ)
(3) インピーダンス(一定値は無理としても、極端な高低は不許)
(4) 偏波面を特定しない
(5) 小型軽量
理論は概略に留めて、カットアンドトライして作成した数々の試作品の中から、上記の条件のを具えながら、より高い成績を得たものを方式化した。
低い周波数では四葉のクローバ形の指向特性で、90度方向をずらせたものを上下に置くことで指向性を改善した。
1個では、水平偏波専用であるが、上下2個の間を明ければ電界の垂直分力が生じて垂直偏波にも感度を得られる。更に、高角(±)の感度幅も拡大する。
周波数の高い領域ではプラタナスかドリアンの実のような、角(つの)だらけの指向特性だろうと思う。
◆サンチ波逆探

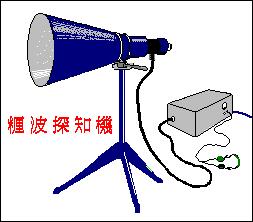 現物は1台だけあったけれども教えてくれる先輩がいなかった。しかし一目瞭然の簡単な仕掛けで三脚上に開口40cm位の電磁ラッパとその後方に茶筒のような伸び縮みできる空洞共振器がついていた。ラッパの奥に広帯域ダイポールが45度傾けて鉱石ダイオードと共に付けられていた。
現物は1台だけあったけれども教えてくれる先輩がいなかった。しかし一目瞭然の簡単な仕掛けで三脚上に開口40cm位の電磁ラッパとその後方に茶筒のような伸び縮みできる空洞共振器がついていた。ラッパの奥に広帯域ダイポールが45度傾けて鉱石ダイオードと共に付けられていた。
スーパーヘテロダインではないと観察した。こんなチャチな物で敵レーダーを回避できるのだろうか?
最近かつての同僚が「先輩から賜った」という資料を送ってよこした。
それによると「探知機3型」と称して糎(サンチ)波逆探が艦船に実戦配備されていたとのこと。
・・・・・・日向新聞 そしてそれは小型のパラボラアンテナが使われていたらしい。
A N 方式を採用した逆探
航空機用電波探索機 「試製2式空7号無線電信機 2 型 ( F T - B ) 」
FT−B の等感度受信方式について
『検知』と『測定』が受信機前面のスイッチで切り替えられる。『検知』は無指向アンテナに繋がる。
『測定』にすると、左寄りと、右寄り2個の指向アンテナに繋がり、後に述べるパターンで左右が切替わる。
電波兵器には珍しいことに、『 A N 式』式等感度受信方式を使っている。
広帯域アンテナは素子が大きく方向精度を必要なまで上げることが困難なので、それを打開する苦心の跡が見える。
『A N 式』は従来から航法無線に使われていた方法で、昭和10〜20年代、無線工学の教科書には必ずあった。その
航法無線では一般の航空機が利用できるようにと、送信側に仕組みを設けてあるので、受信機に仕掛けは要らない。
しかし、この電波探索機 FT−B が A N 方式で受信をするためには受信機側に仕組みが必要。
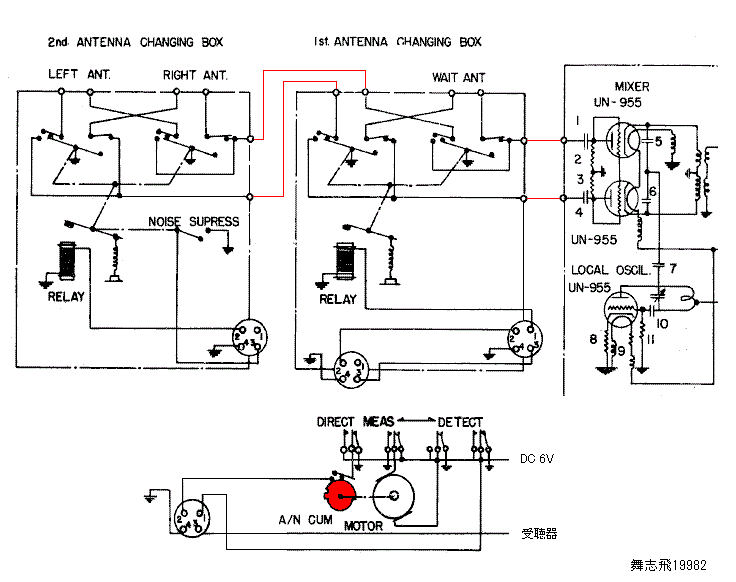
モールス符号の『 A 』は「トン ツー」で『 N 』は「ツー トン」。
A符号を繰返し送っていたとする。そして、この符号の on off を反転したものは N の繰返し符号になる。
この2つの繰返し符号を同じ大きさで同時に重ねて聞けば、切れ目のない連続音になる。これを利用したのが A N 式。
A N 式 そのアイデアは、まさに等感度方式、更には自動制御方式の元祖である!
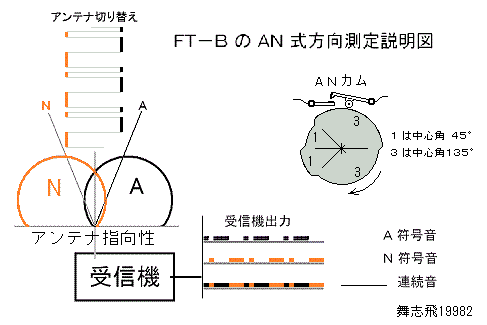
目標を左に外す(機首右寄り)とモールス符号の『 N 』が聞こえ、
目標を右に外す(機首左寄り)とモールス符号の『 A 』が聞こえる。
目標に正対すると連続音になって聞こえる。
受信機本体も特殊で、入力回路に周波数選択機能を持たせず、反対側ヘテロダインその他、あらゆる『スプリアス感度を
積極的に利用している』。
設計に当時の戦線の緊迫化が窺える。
『スプリアス感度を積極的に利用している』=探知範囲拡大に聊かな期待! 関連記事
中間周波数を25MHzと高くしているのもUHF上部に持駒がない苦策!
計器指示を採用した逆探
航空機用電波探索機 「試製2式空7号無線電信機 2 型 ( F T - C ) 」
FT−C の左右指示方式について
回路図を解読して動作の概要が把握できた。
なにしろ、図面の精細度が低くまた誤写と思われる不合理箇所があり推測で補わなければならなかった。
その結果、無指向性アンテナ受信の場合と指向性アンテナの左・右を継電器接点で切替比較して方位を定める点に於いては、FT−Bと全く同様である。
異なる点は、方位を零中点の電流計指示によって+,−が左,右を示す方法を採っている。したがって左右アンテナは交互等時間交代である。
“入力回路に周波数選択機能を持たせず、反対側ヘテロダインその他、あらゆる『スプリアス感度を積極的に利用している』。” ← 前者同様
◆電波妨害機
敵電探に捕らえられようとしたとき、彼の周波数に合わせて
激しく乱雑を付加した電波を返す電波兵器。
敵サン だけのものと思っていたが、友軍にもこの種の兵器があったらしい。
海軍での呼称は「妨信装置」。戦果の有無、配備状況は知らない。
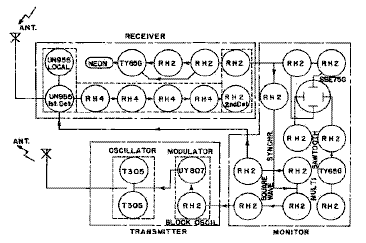
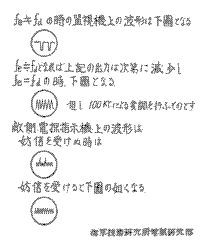
左図は米軍が日本軍解体の際調査作成したのもの、 右図は日本海軍技術研究所