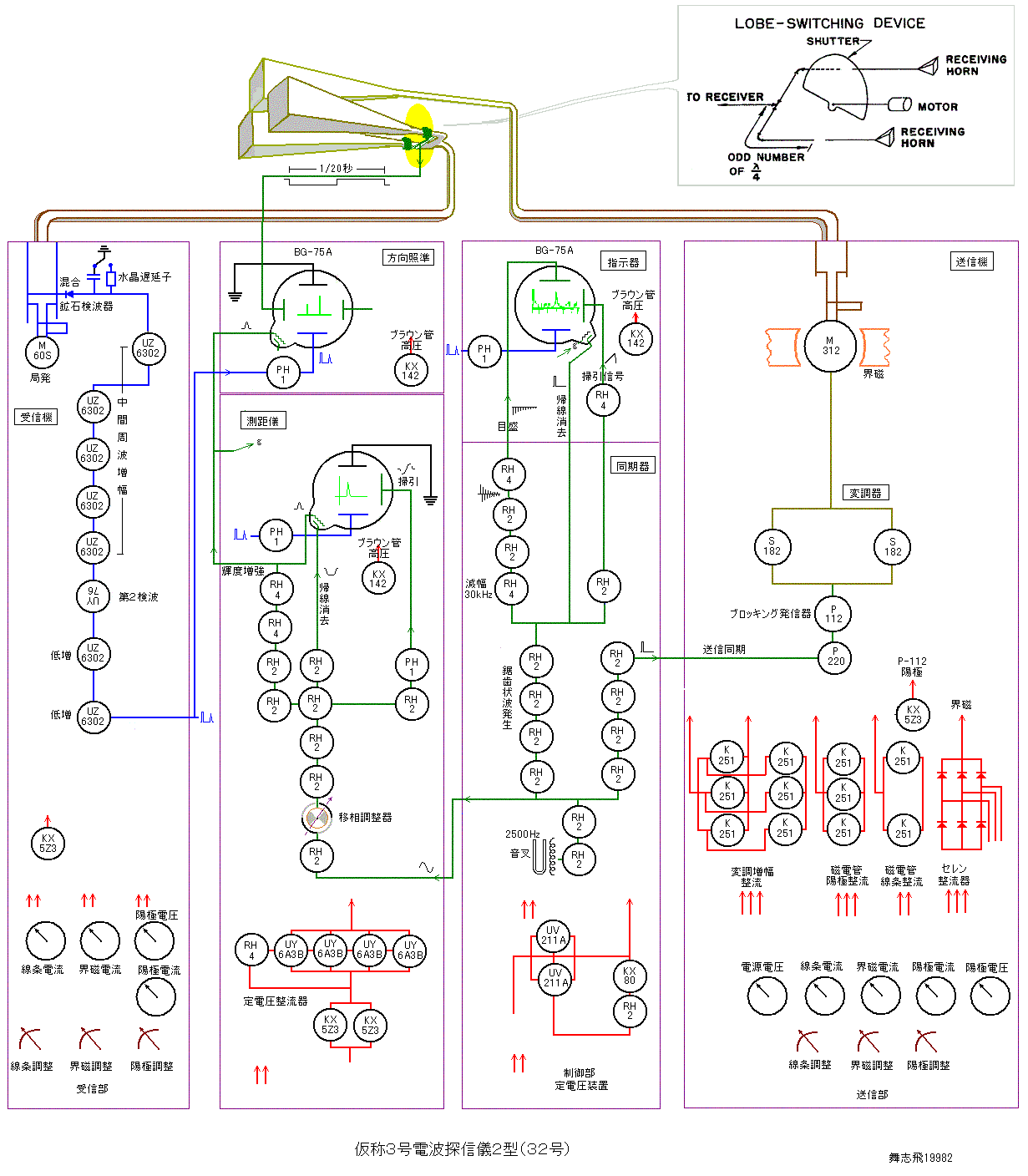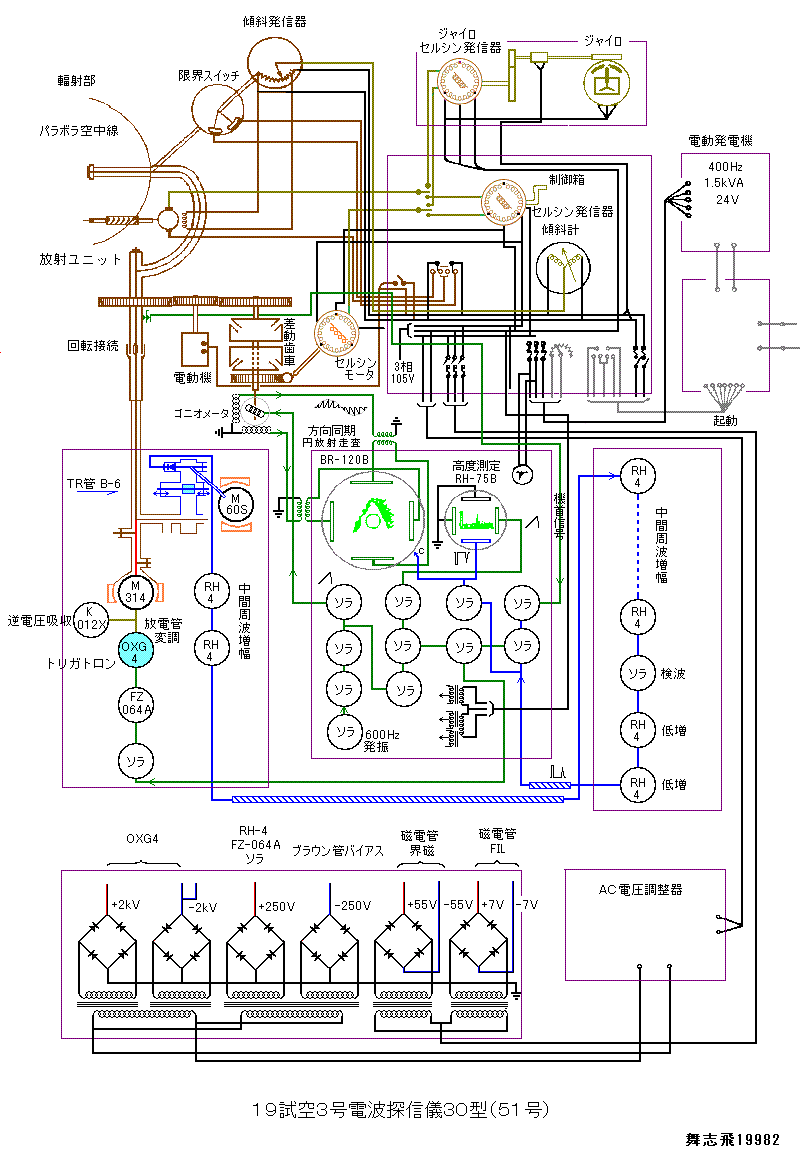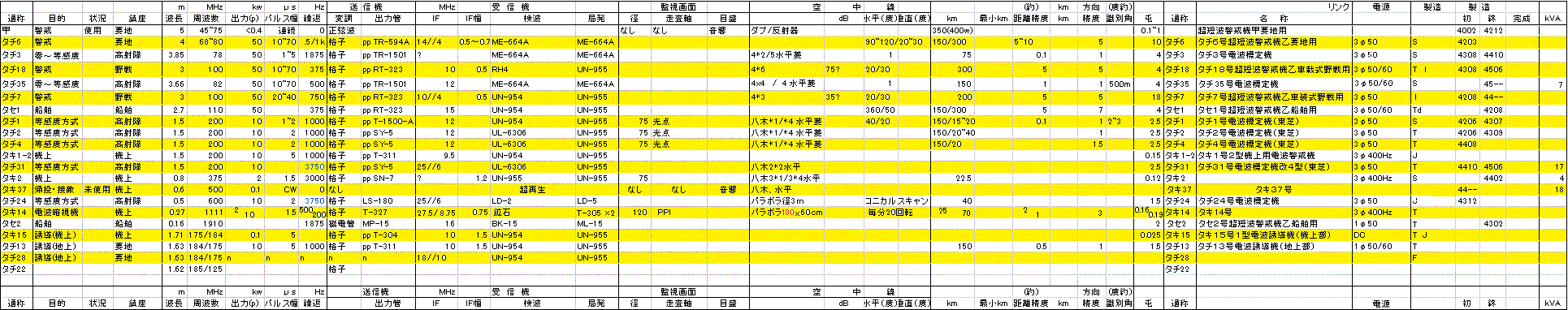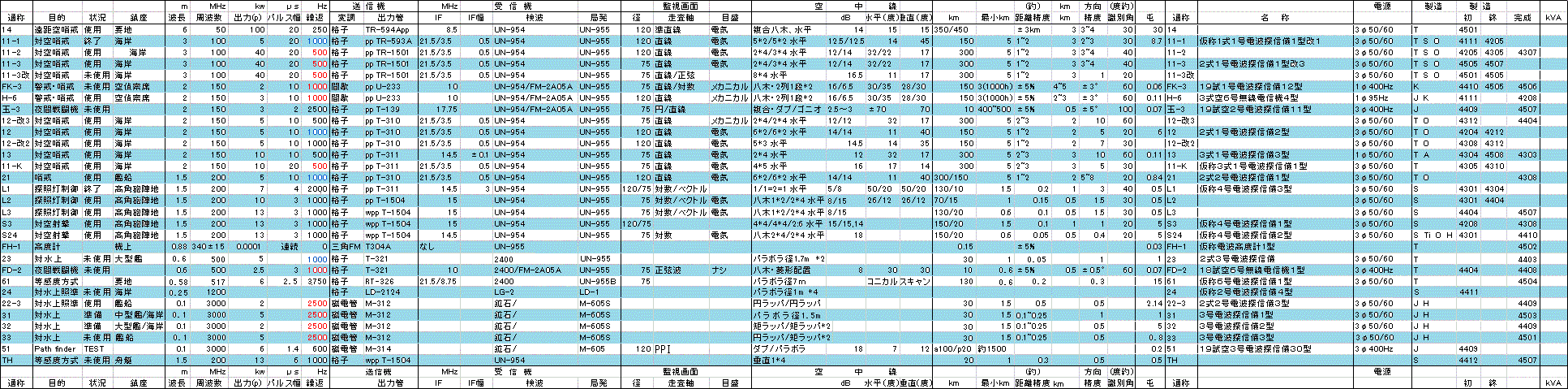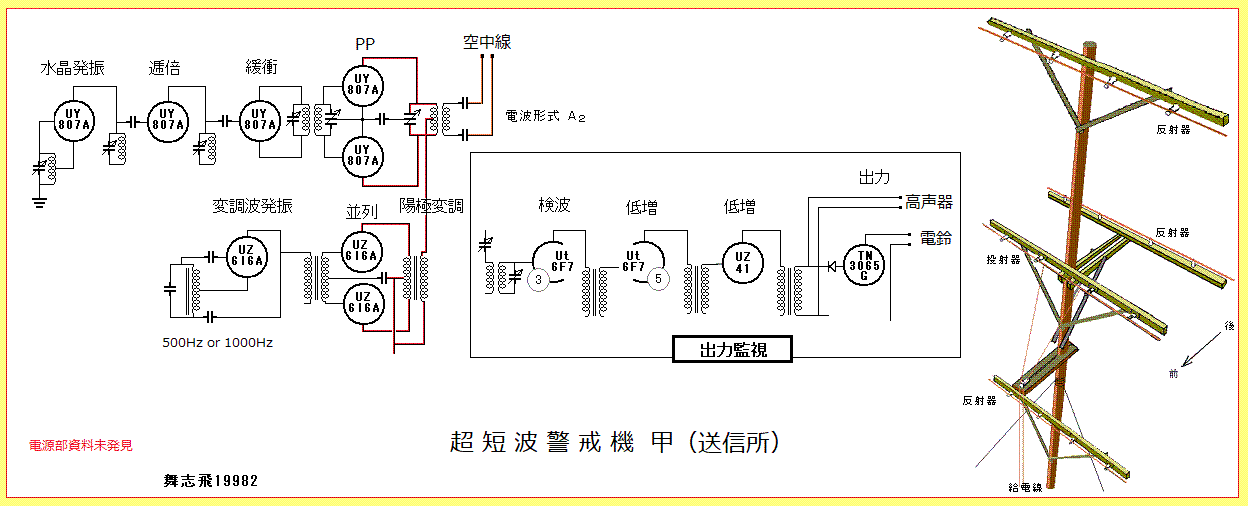
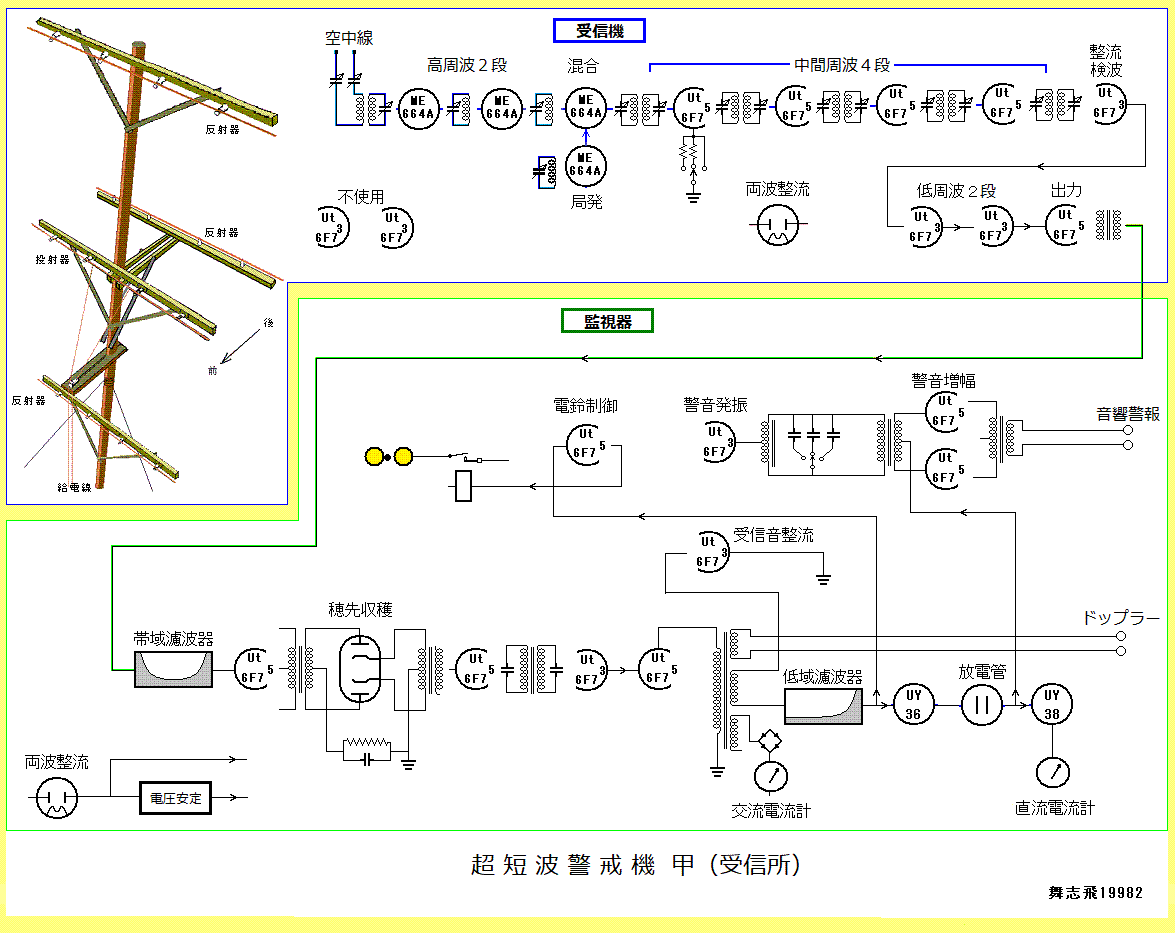
『穂先収穫』は、茎の高さを自動判別して穂を収穫する。
ドップラー効果利用 海軍は試みたが、採用しなかった。
送信点または受信点を艦船上に置けば、陸地、島など固定物体の反射電波はすべてがドップラー効果を生じて判別できない。
「公開された米軍調査資料をなぞったものではないか?」 まさに然り!
部分的に欠損がある場合は推定して埋めた。
原資料中の間違い部分は不合理を解消させた。
理解の便利のため図面内で配置を入れ替えた箇所がある。
理解の補助として随所に注釈を付加した。
注記を翻訳した。適宜な着色をした。
改変・補足は着実を期した。
順序は陸軍、海軍及び種別を問わず第1に周波数、第2に古いものからの順番とした。 但し、
誘導乃至バッジヂシステムに関するものは後に置いた。
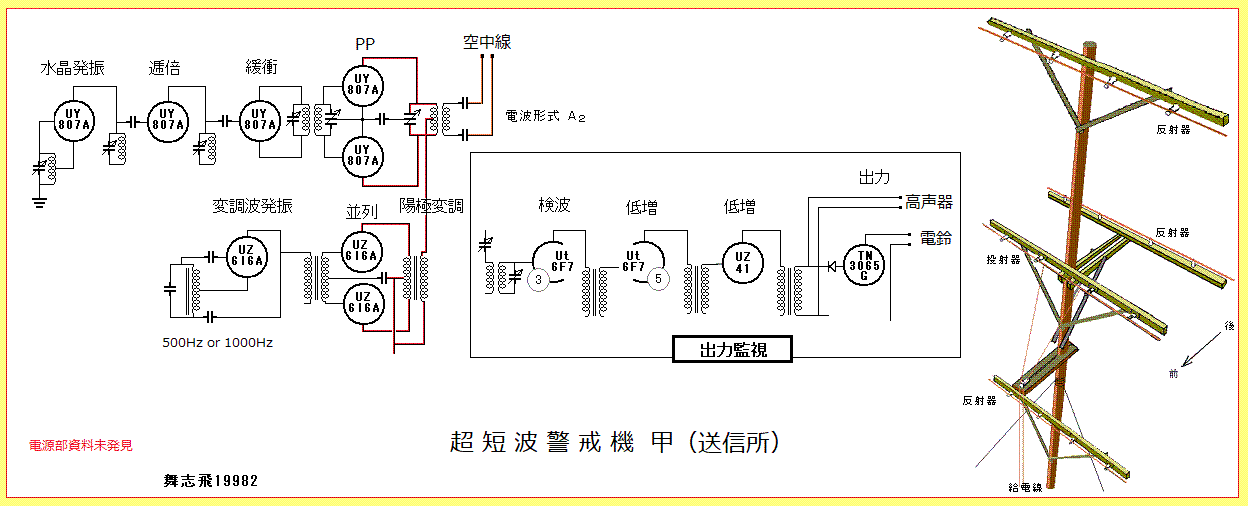
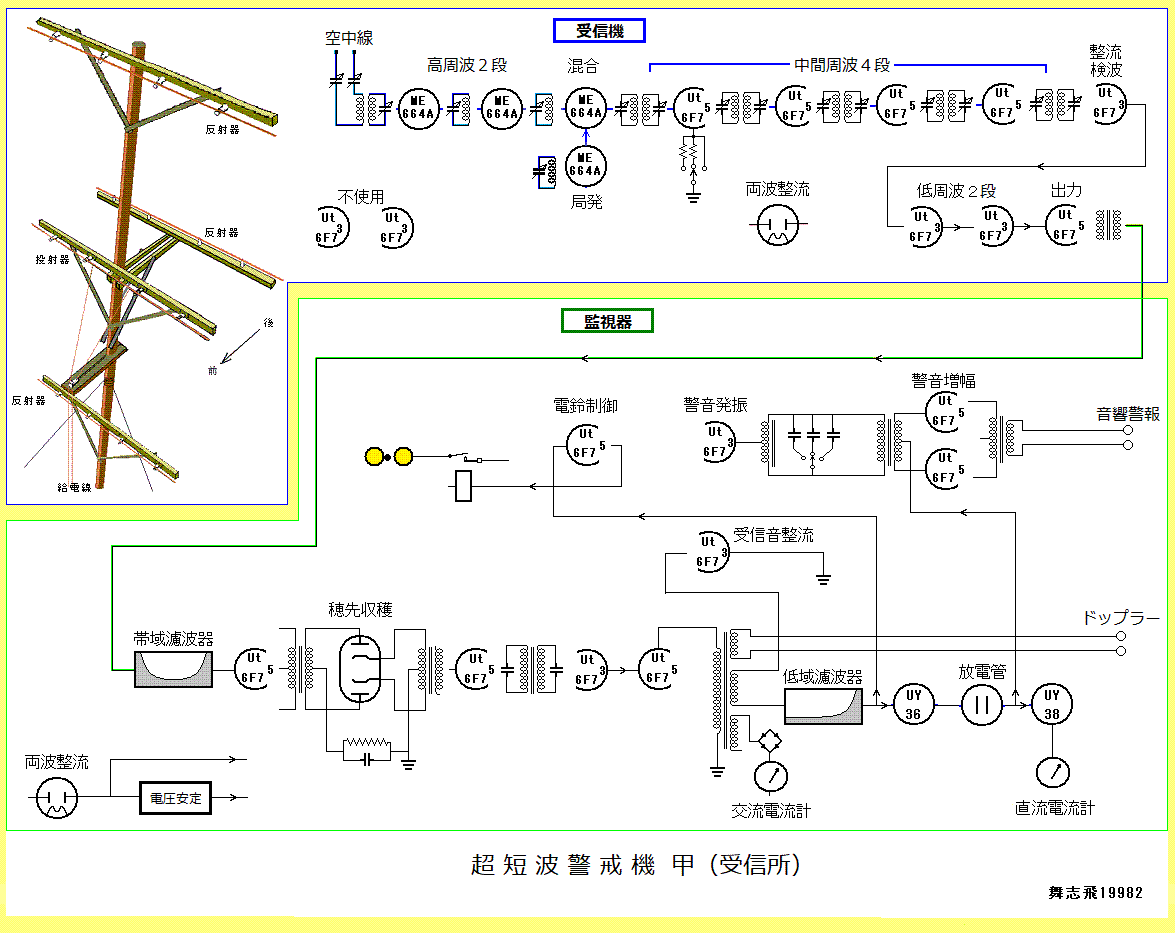
『穂先収穫』は、茎の高さを自動判別して穂を収穫する。
ドップラー効果利用
海軍は試みたが、採用しなかった。
送信点または受信点を艦船上に置けば、陸地、島など固定物体の反射電波はすべてがドップラー効果を生じて判別できない。
アンテナ形式を「絞射空中線」と特別呼称しているが、八木アンテナの2列2段である。
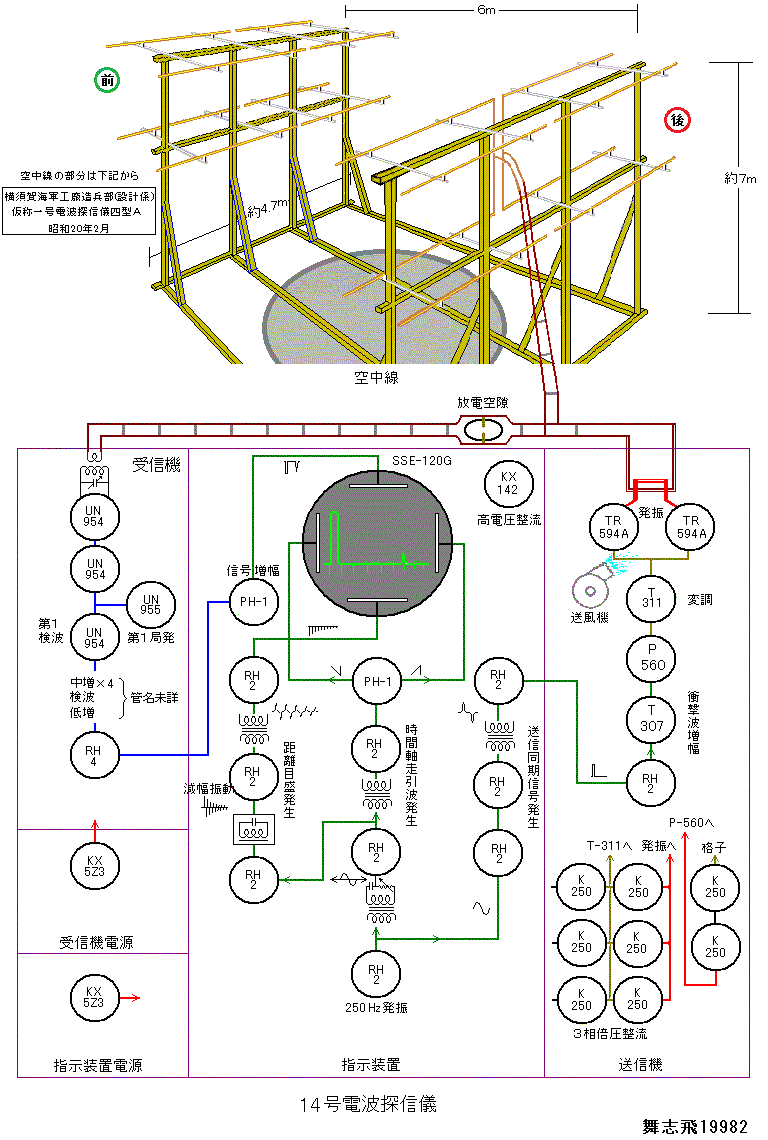
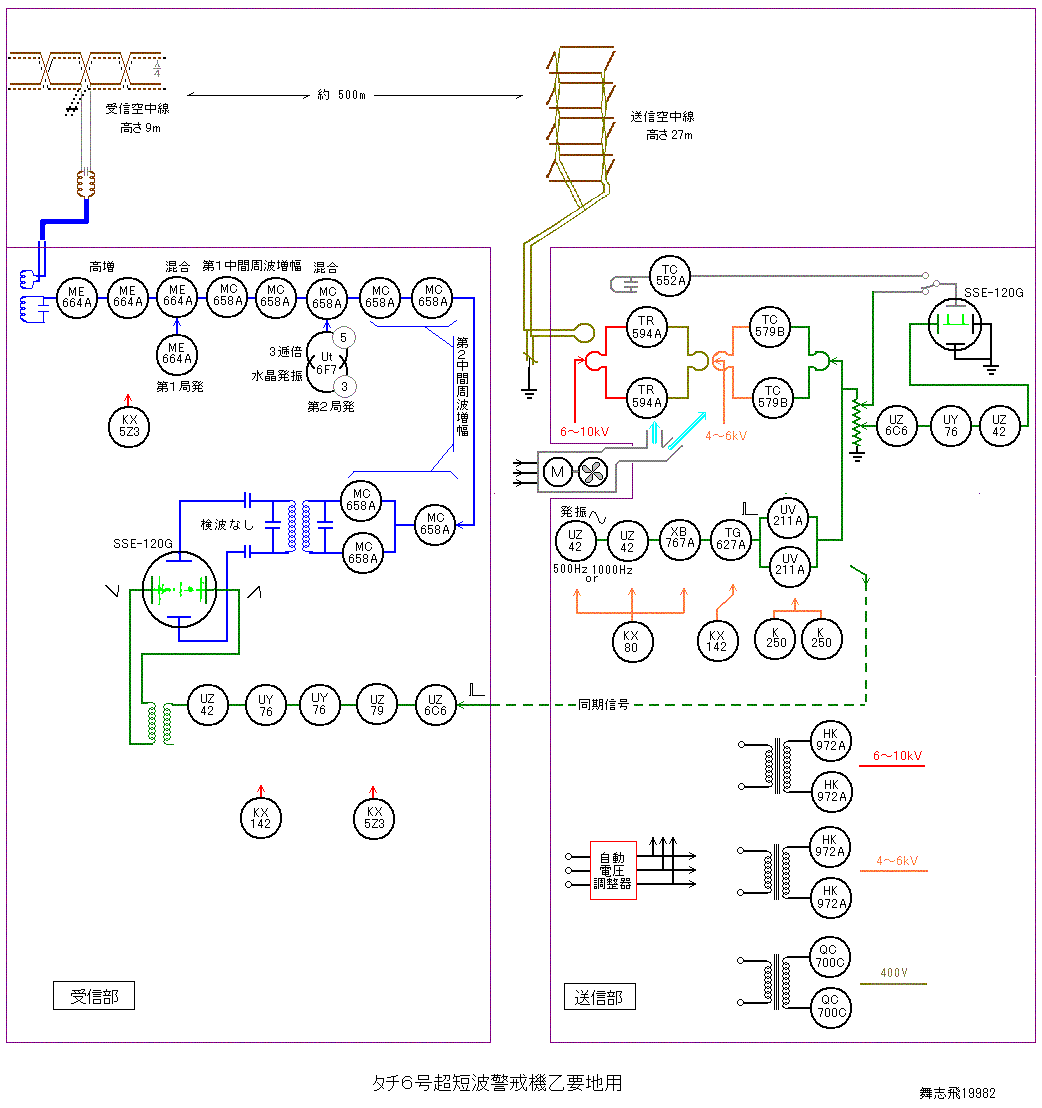
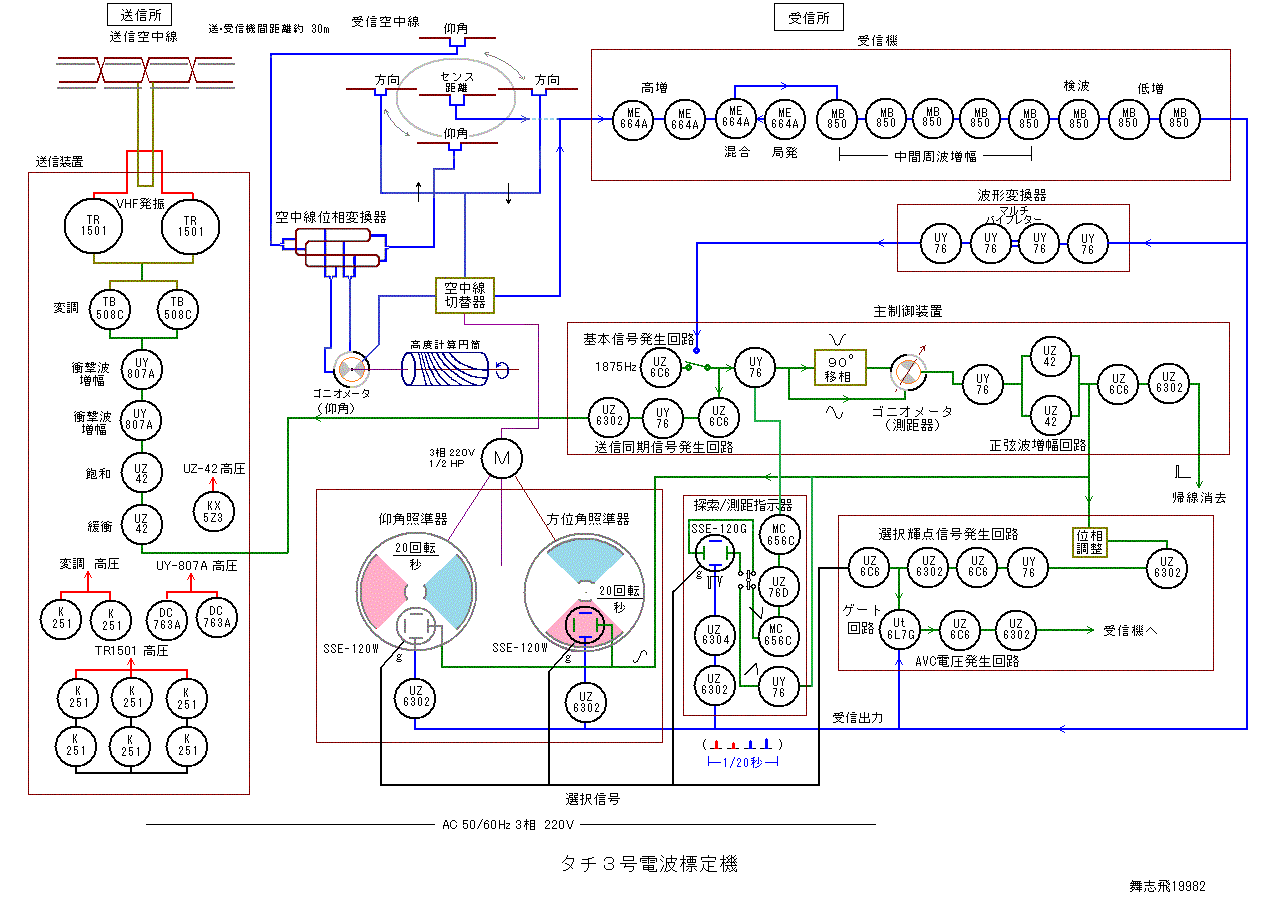
"The horizontal arrangement of the receiving antenna gave greater elevation accuracy at high angles of elevation."
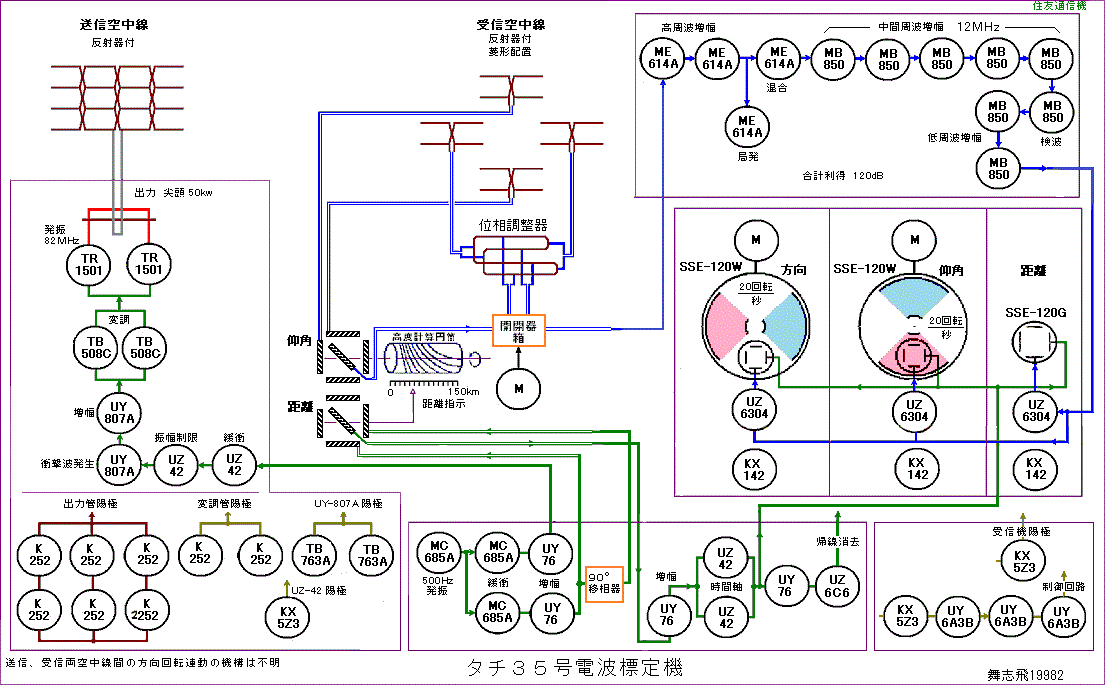
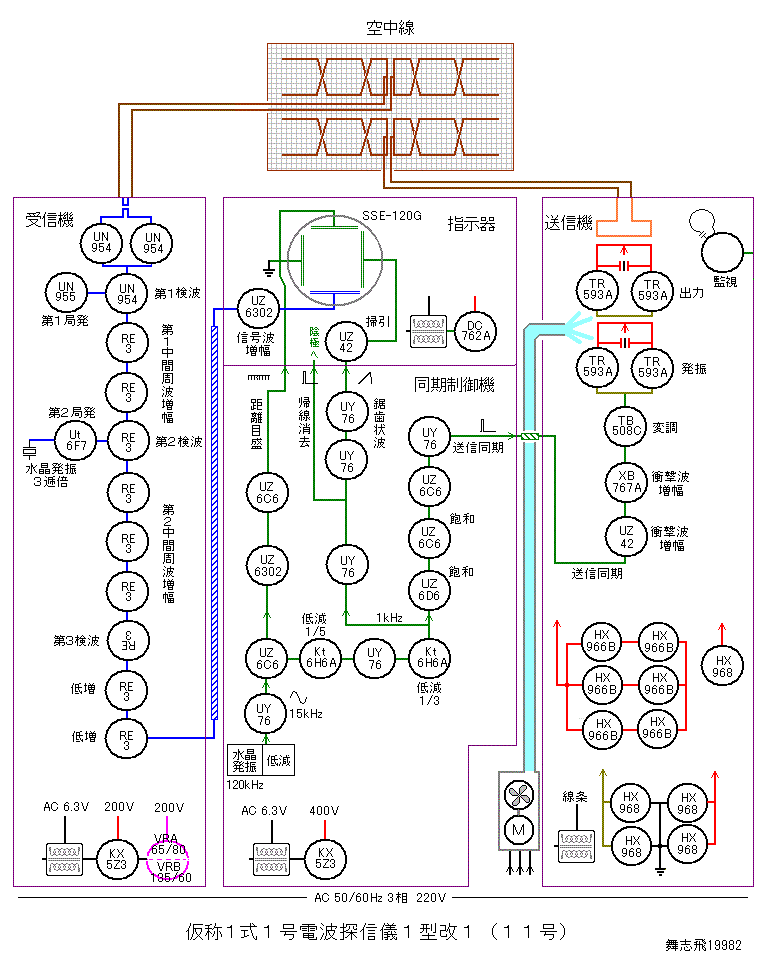
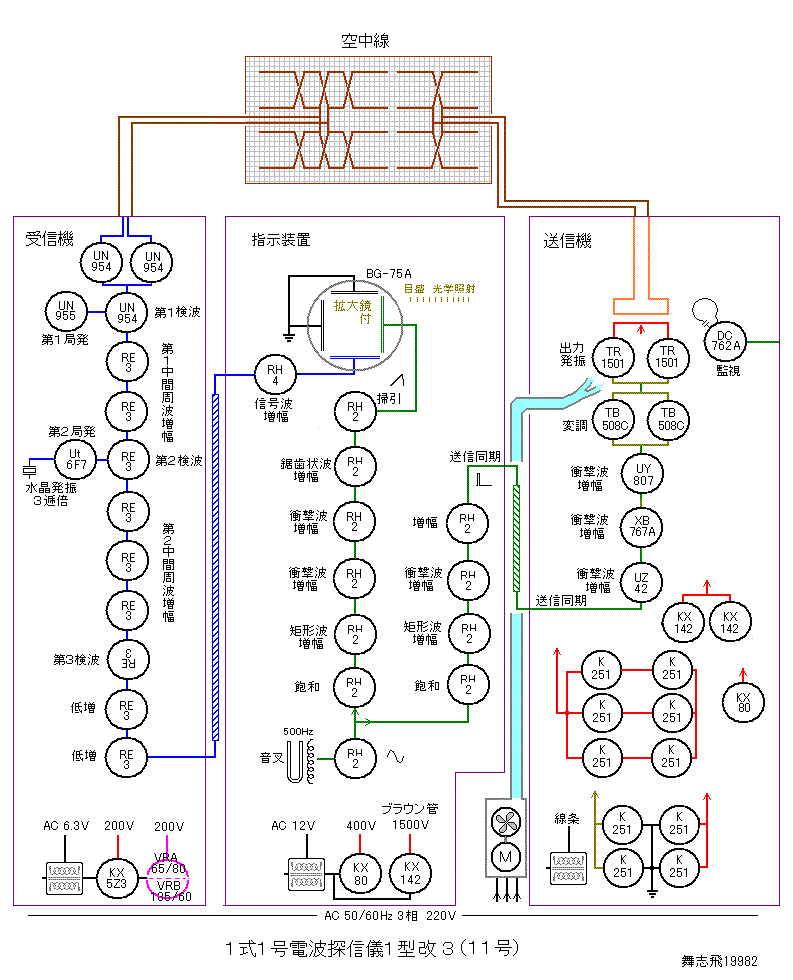
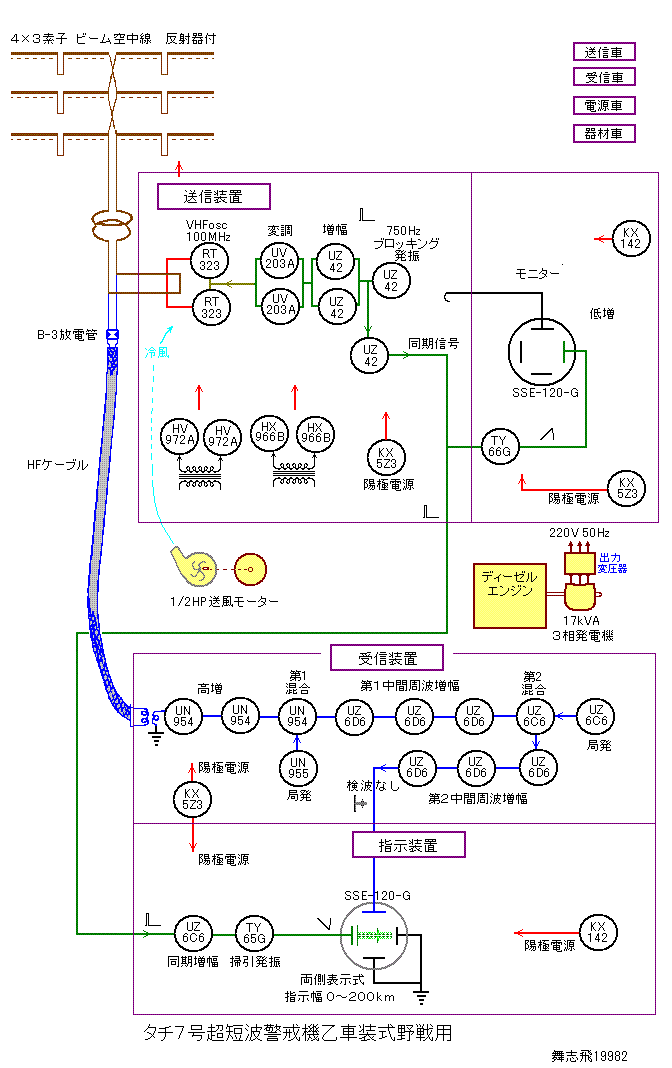
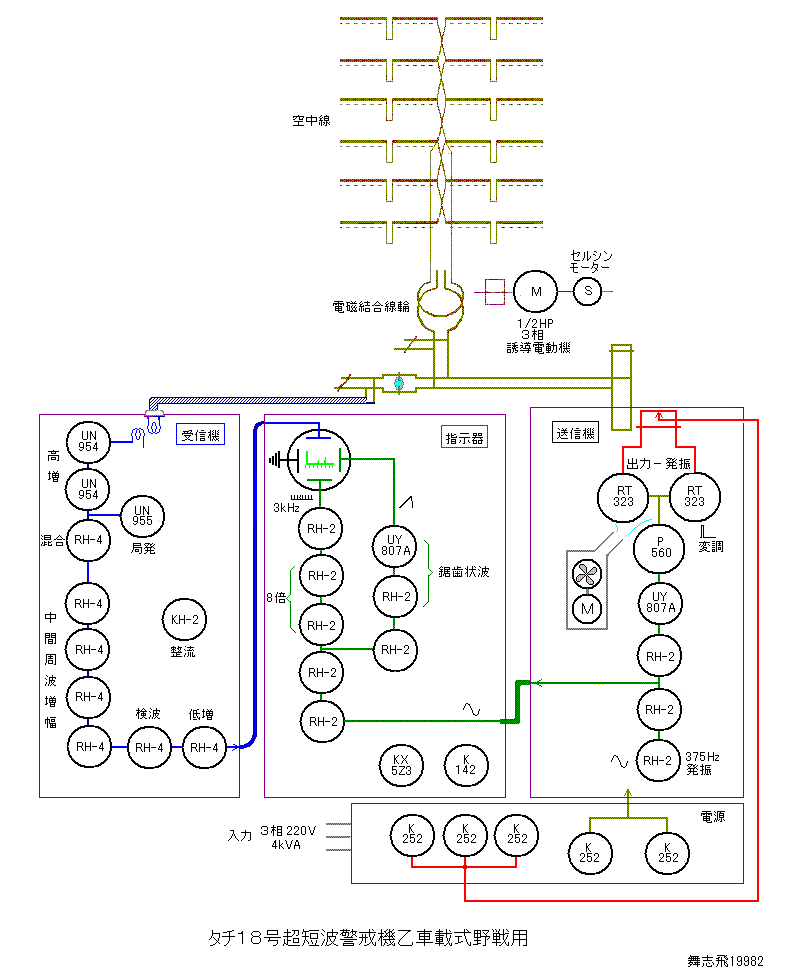
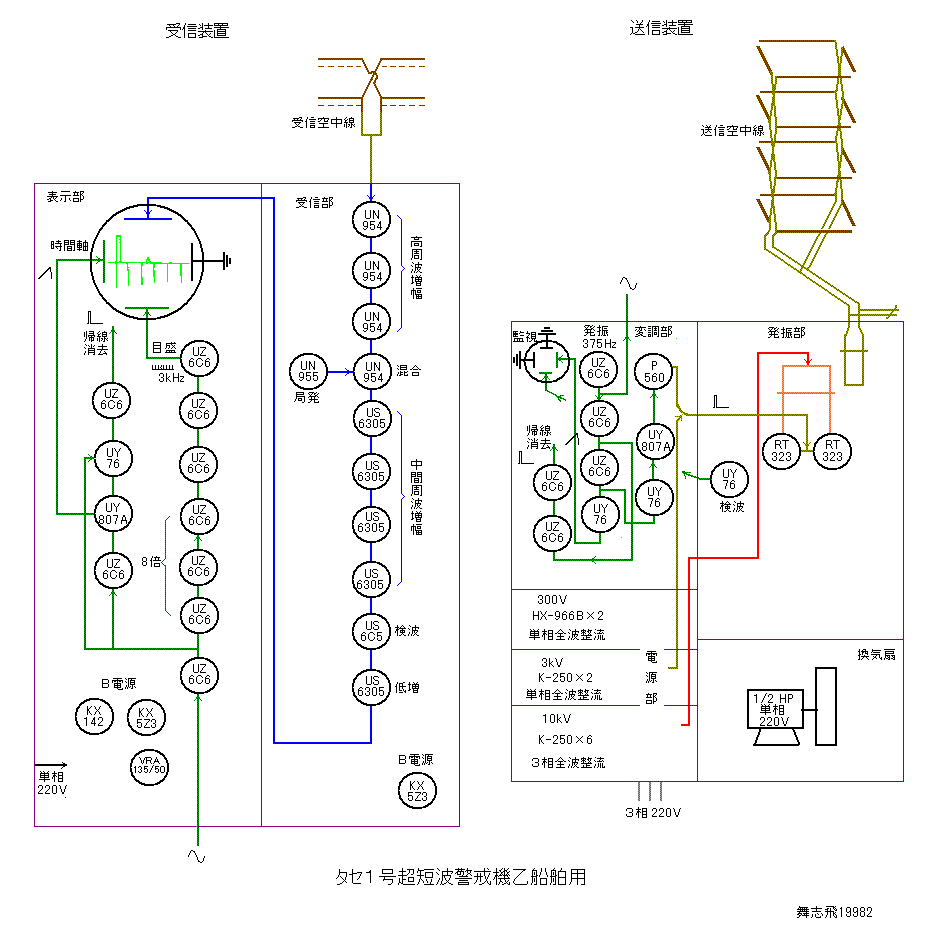
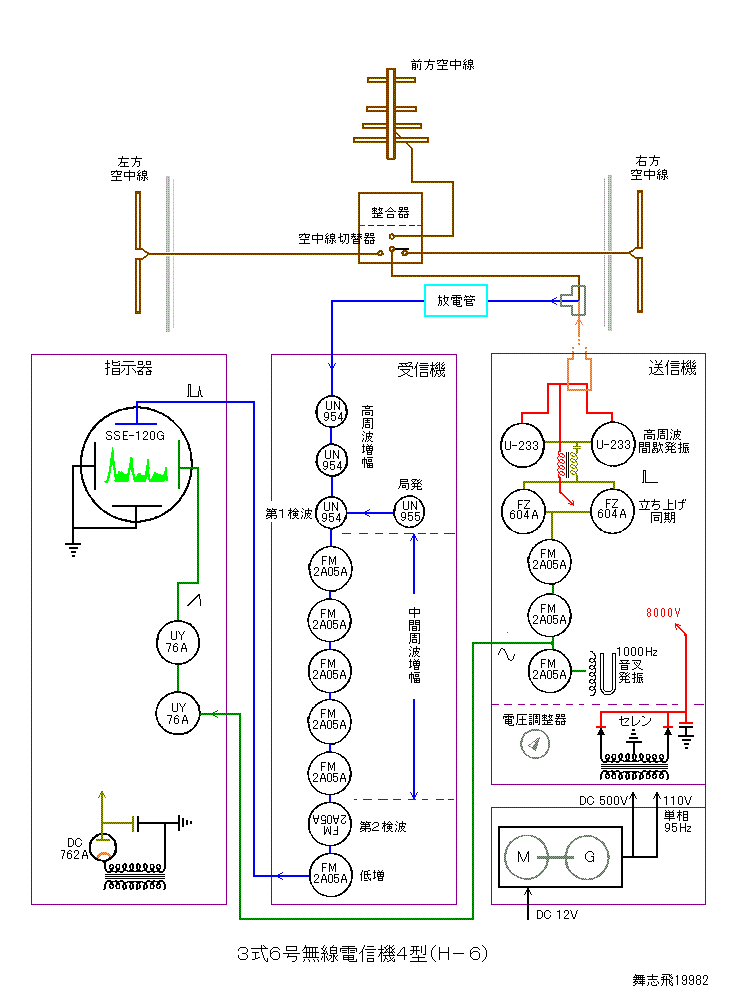
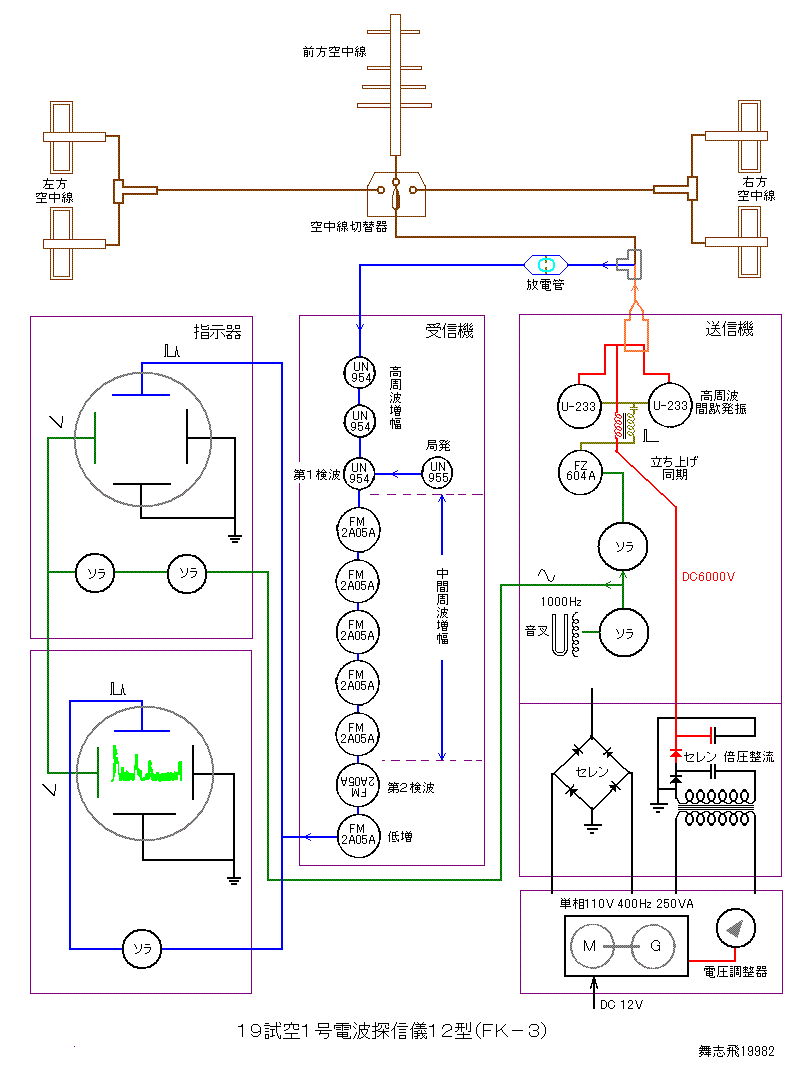
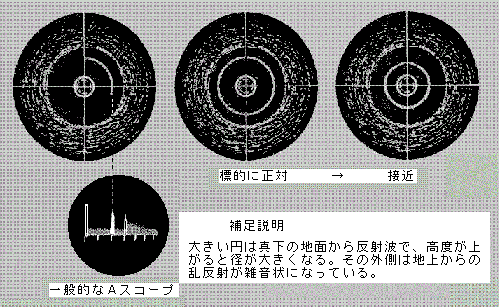
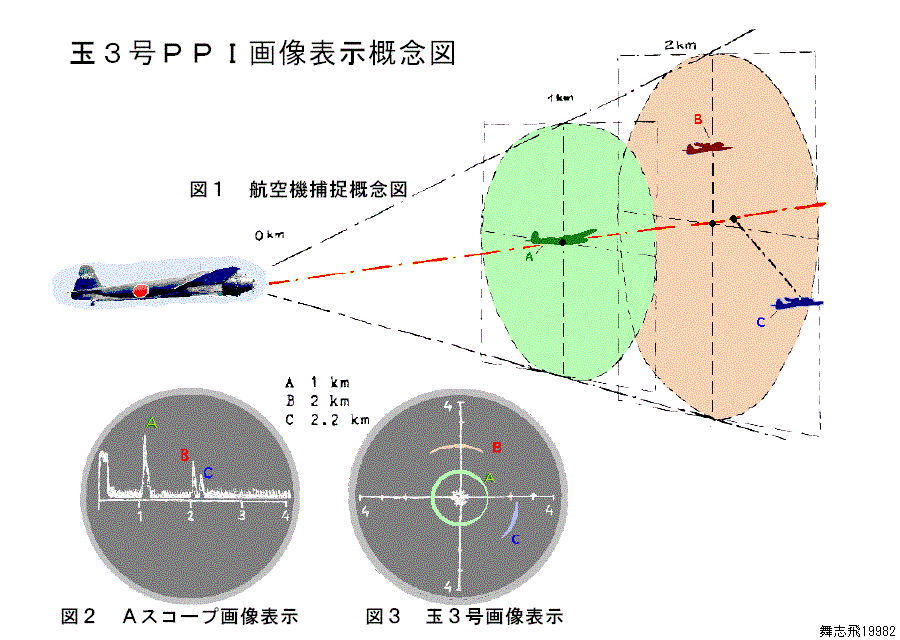
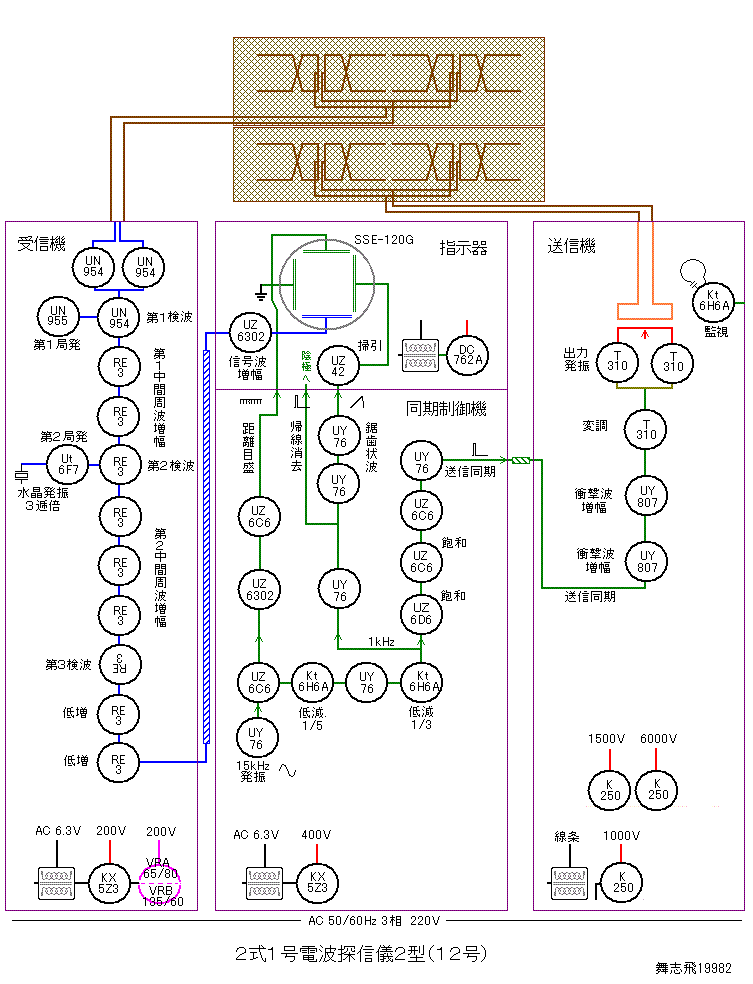
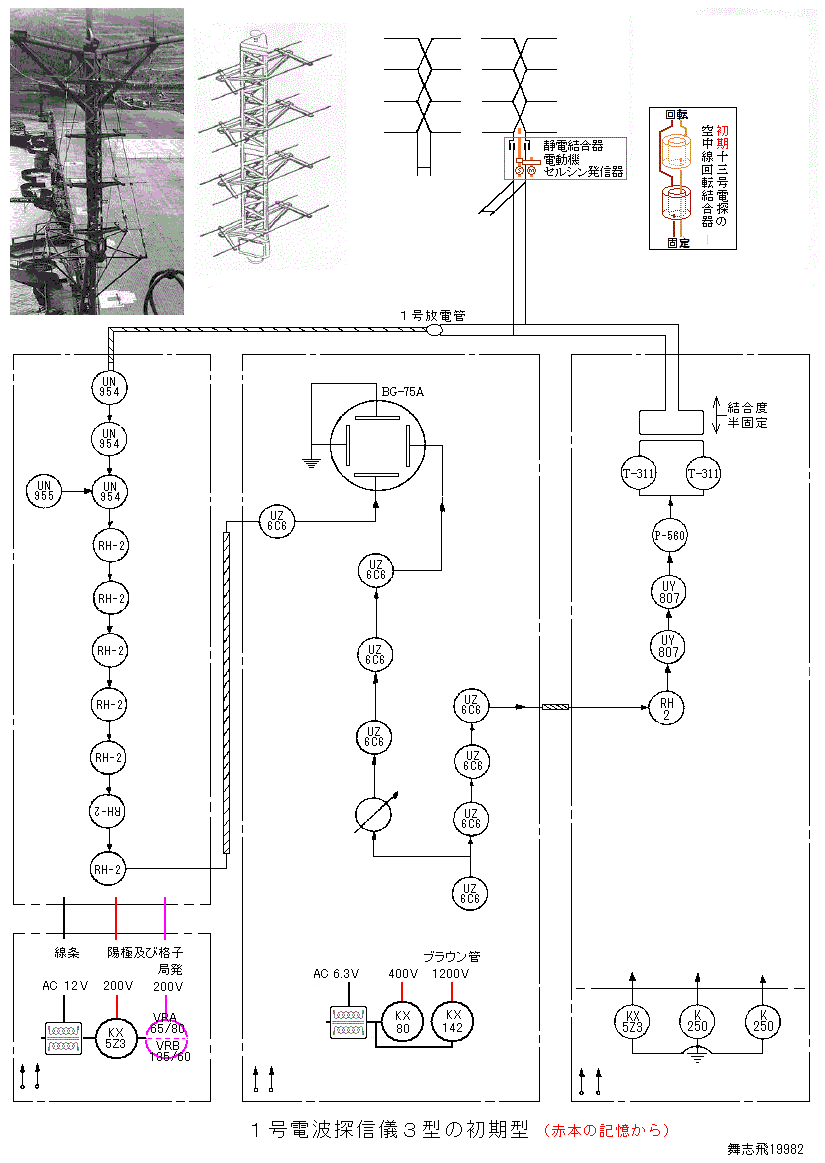
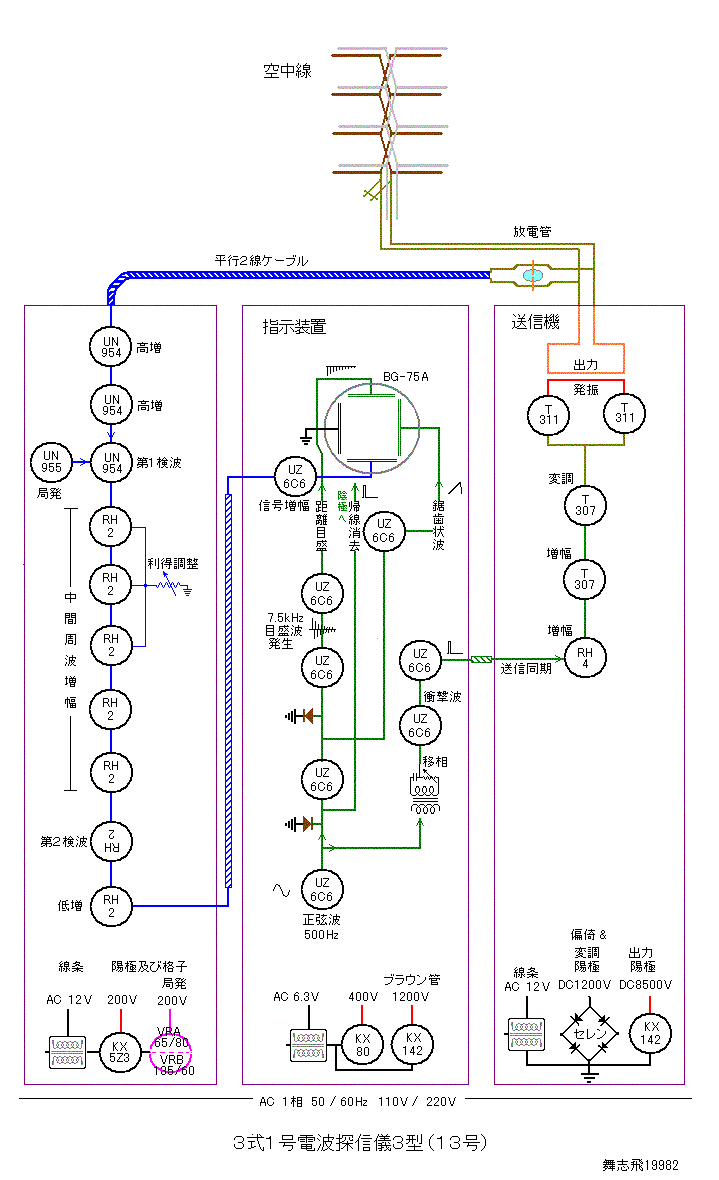
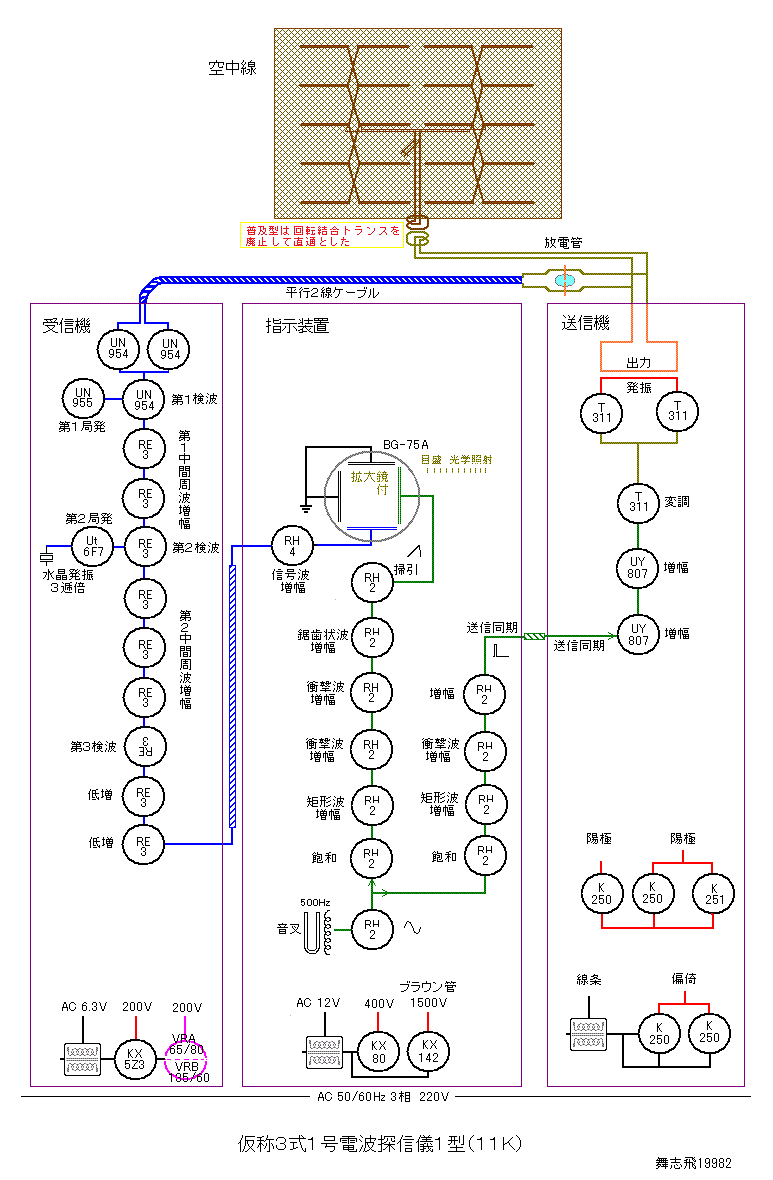
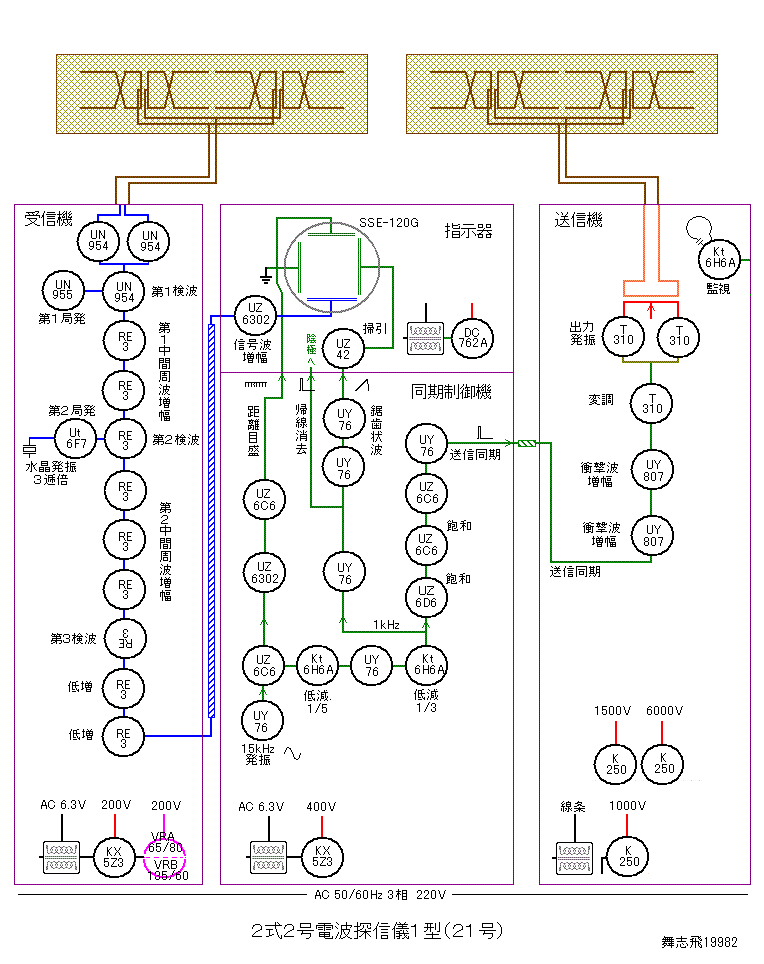
21号電探に出力増強と方向、等感度方式、測距儀を付加した機種を213号電探と称した。
そこに使用の測距儀のからくりを推測
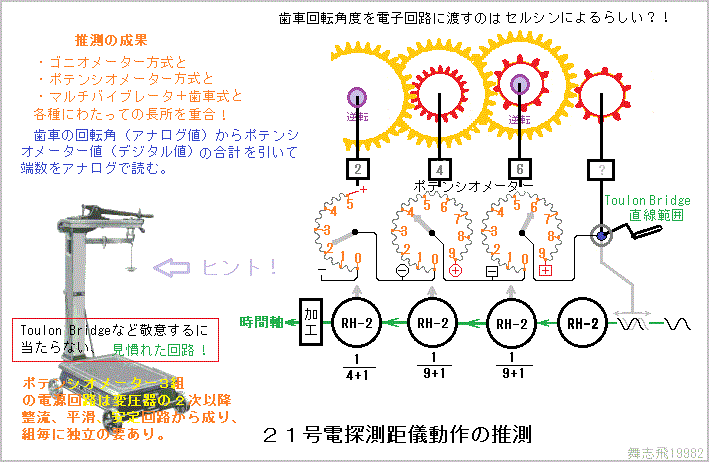
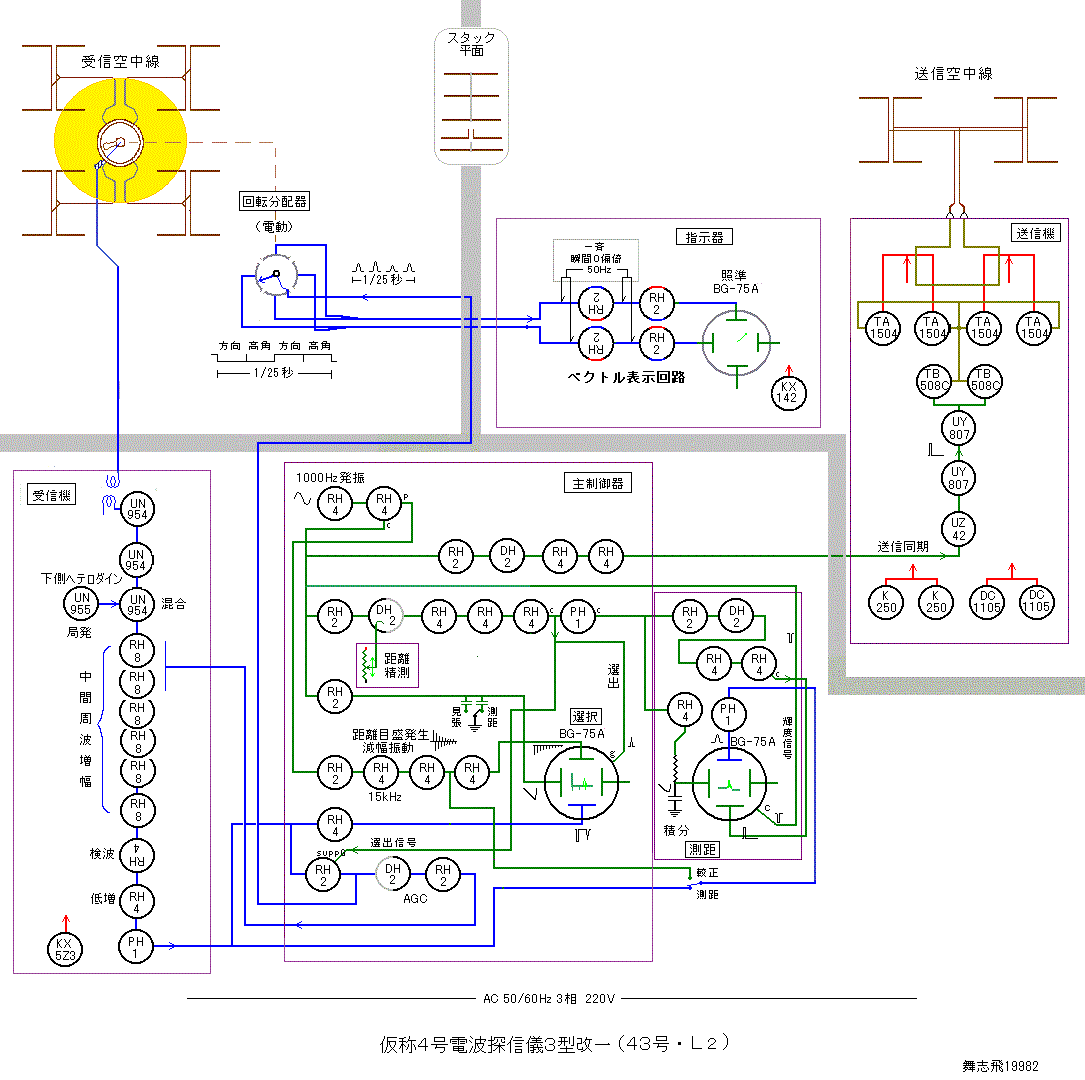
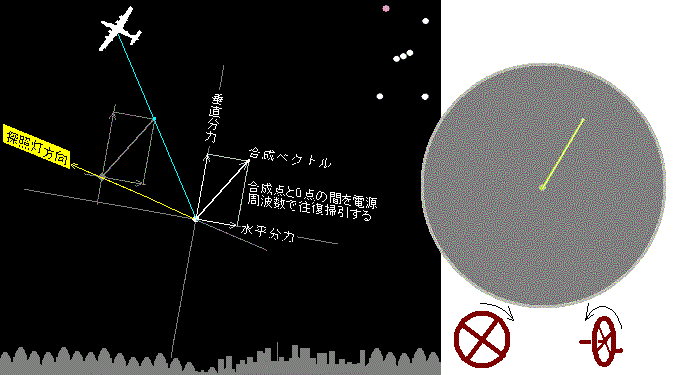
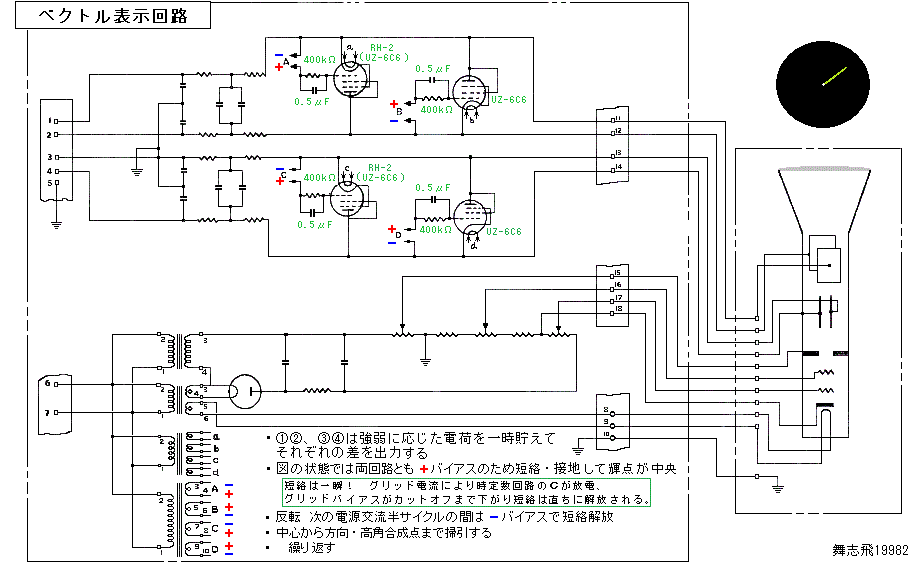
畢竟、この回路の動作は、「直並列変換」にほかならない!
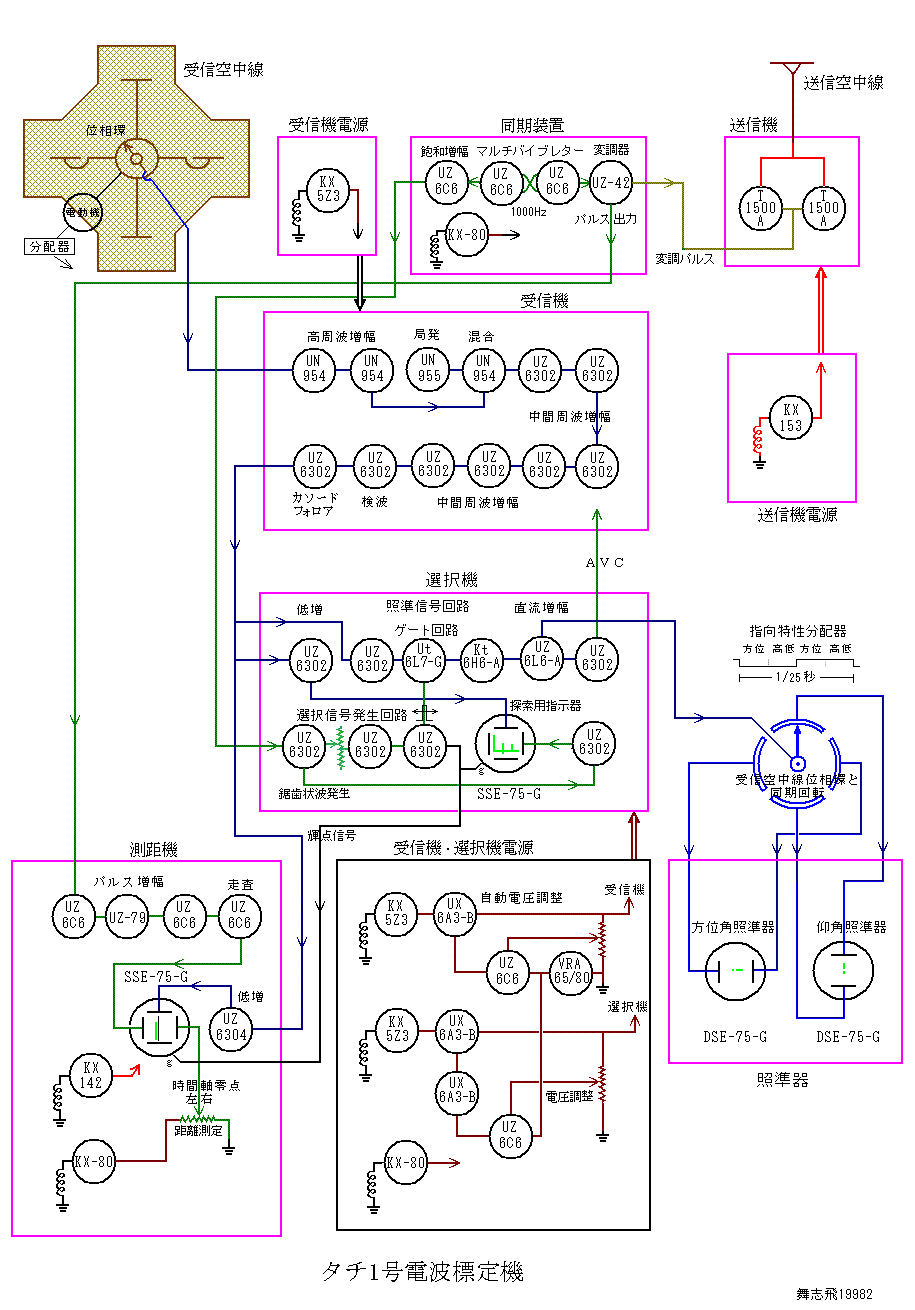
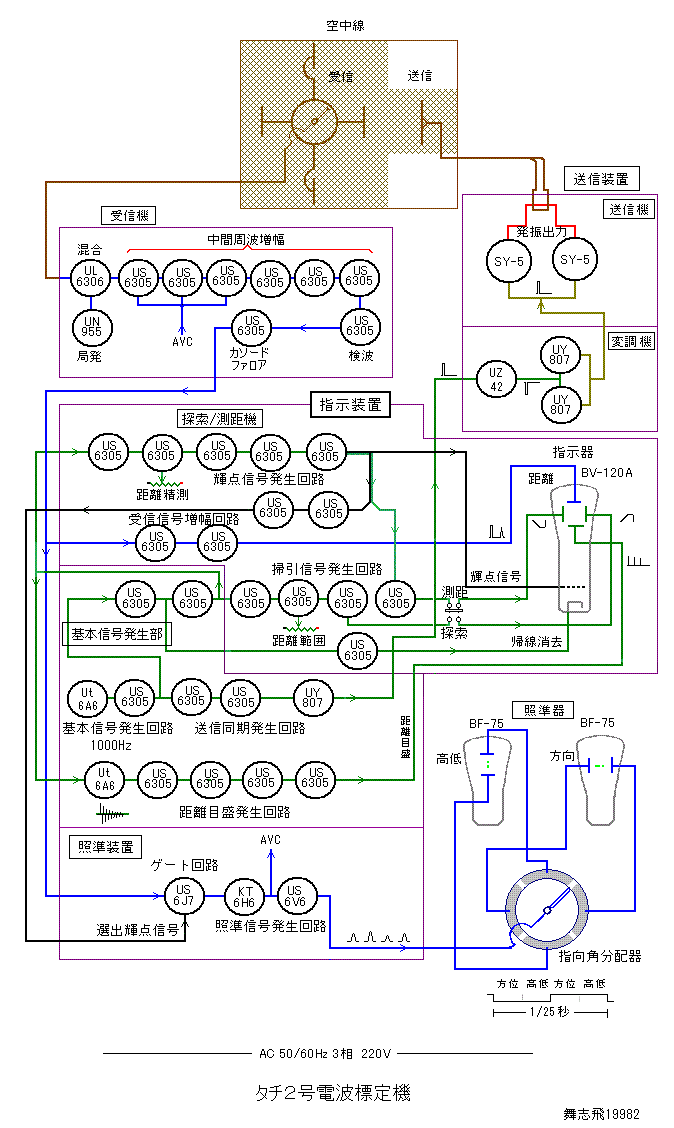
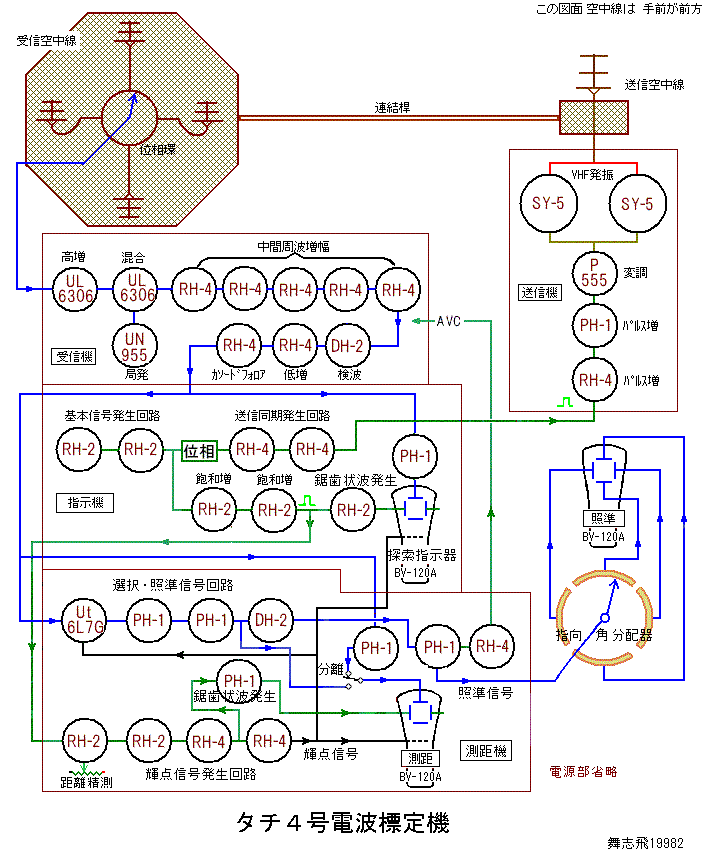
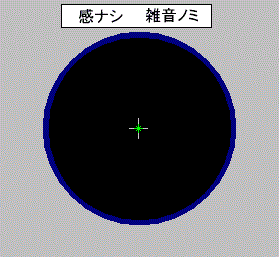
タチ4号標定機の照準管の表示を推理する。
直列並列変換回路が見当たらないのでベクトル表示ではない。
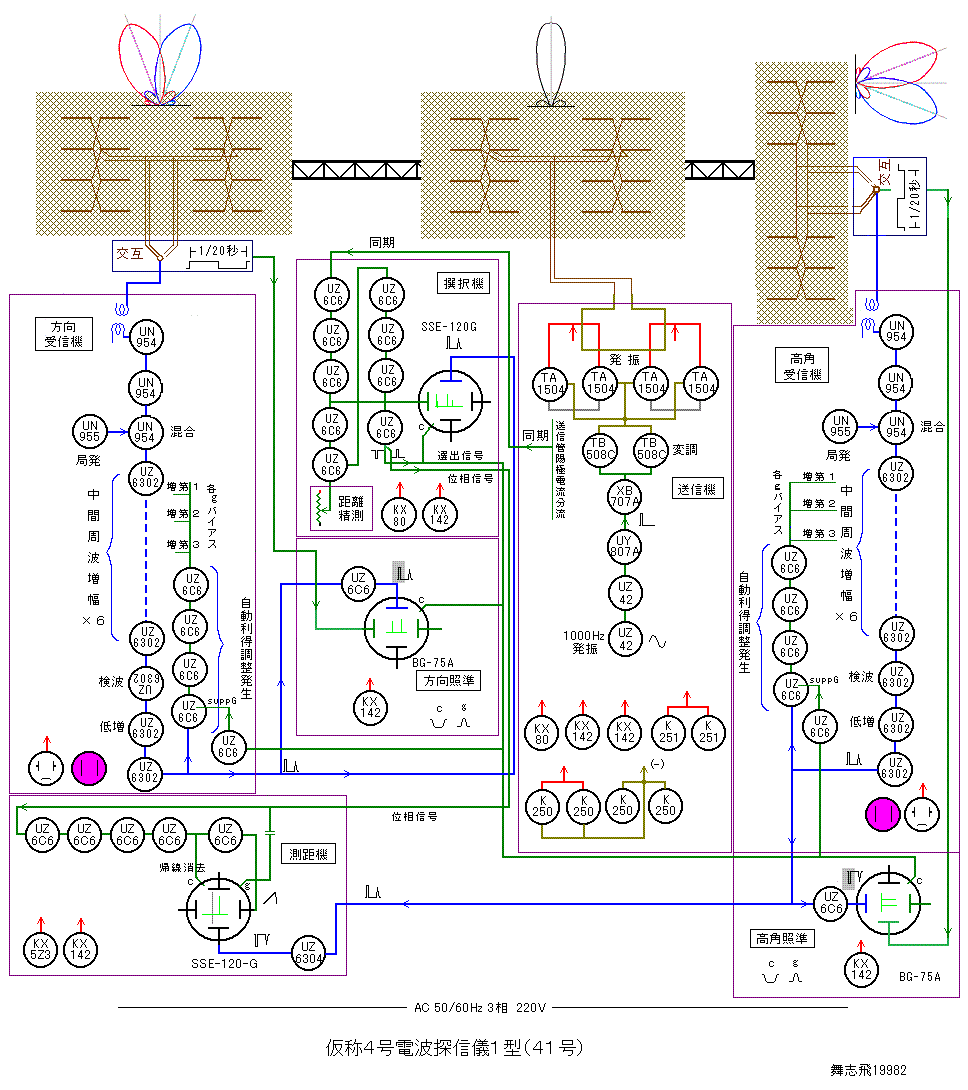
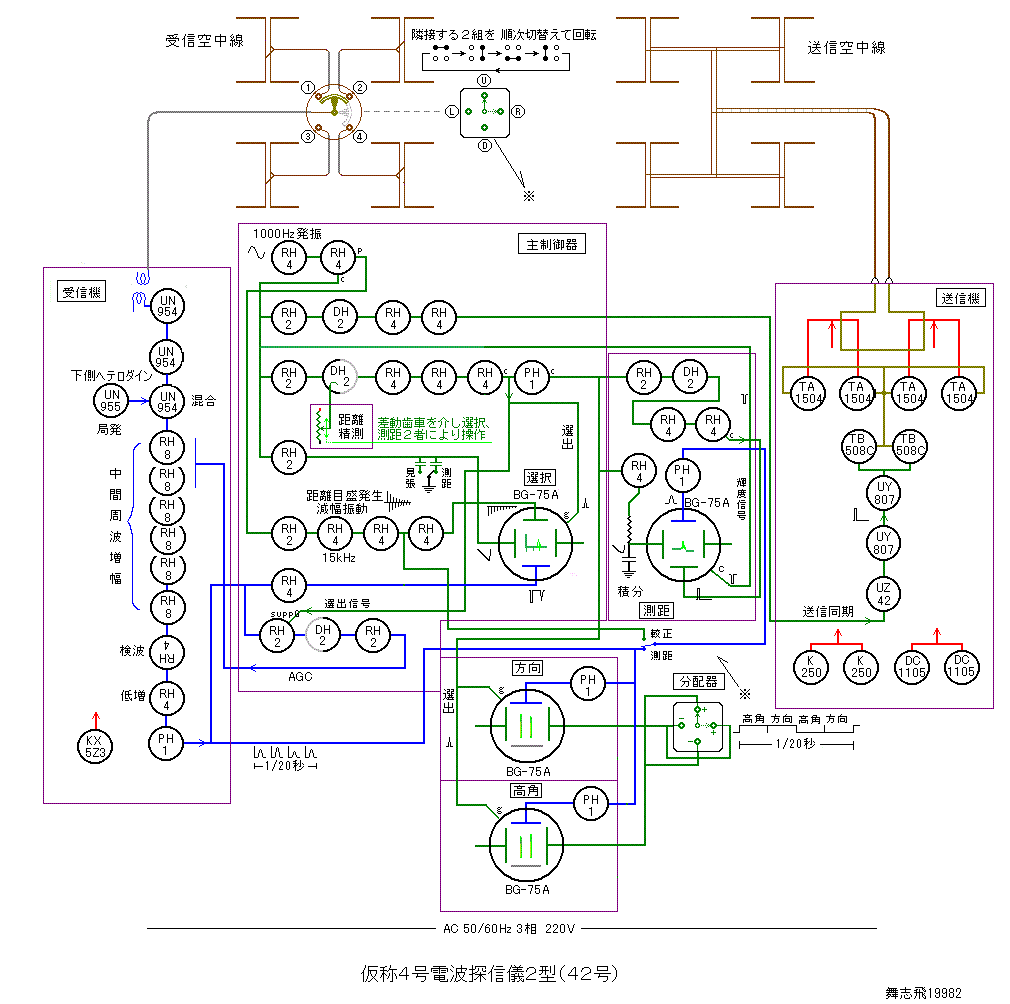
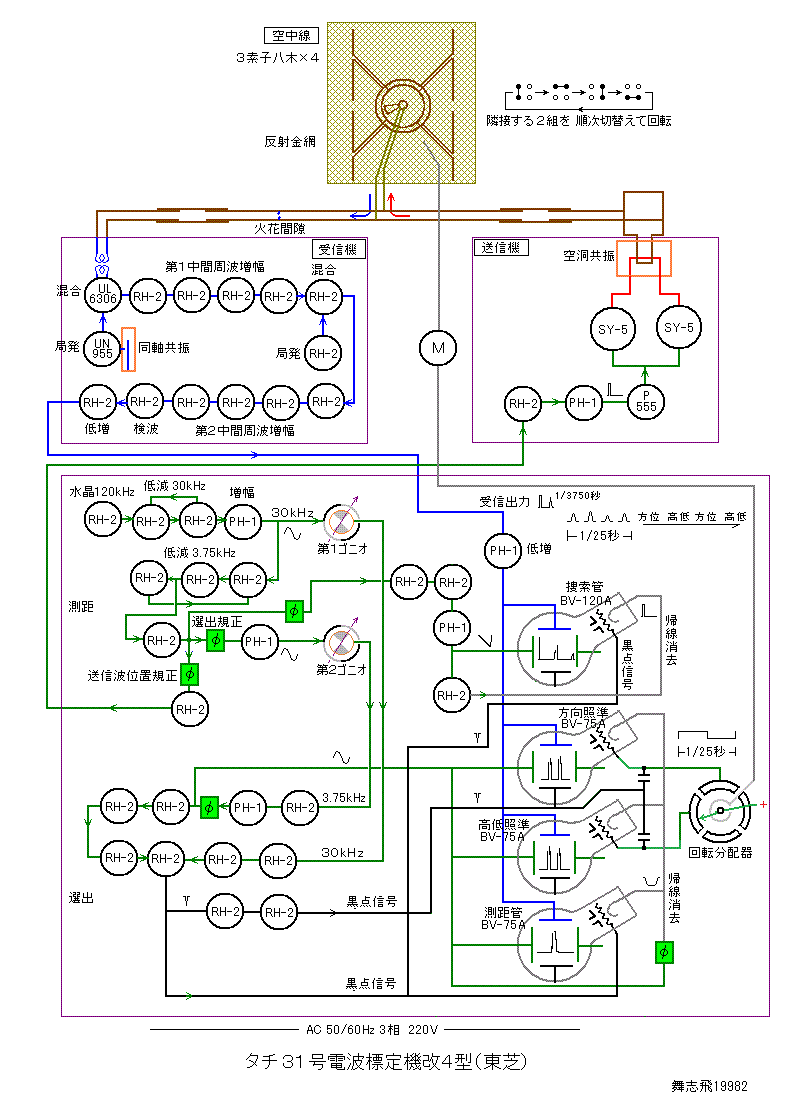
反射パルスによる距離測定
「距離測定は反射波の立ち上がりで測定せよ」 練習生は時間軸の基点から反射パルスのてっぺんまでで測定したがる。 実習中 教官・教員は反射波のてっぺんで測っていつのを見つけるとヤカマしい。 哨戒電探の場合は立ち上がり点と最高点では1キロメートル程度の差で間違っても大したことはないが射撃用電探では間違いは許されないからだ!
ところが、
ドイツからのウルツブルグ方式導入の射撃電探ではマーカである黒点を反射パルスの頂上にあわせて測定するよう指示されている。
この違いをどう納得するか
射撃電探では哨戒電探に比べてパルスの時間幅は狭くて、2マイクロセカンドとすると距離にして300メートル、立ち上がりとパルス中央では150メートルの差が出てしまうではないか?
あ、そうか!! 送信同期と時間軸の位相差を調整する際、ゼロ位置調整は、このときも、 立ち上がりでなくてパルスの中央を使えばよい!なにも悩む必要は無かった。
しかしその際には近傍反射が影響しないよう受信機利得を飽和しなくなるまで下げなければならないな!黒点信号について考察
従前の選択信号は画面上の選択した受信パルスの強調が目的で、信号時間幅は使用パルス幅より広いものであった。
ウルツブルグ方式で使用する黒点信号は送信パルス、受信パルスの幅の内側を探って振幅最大点に合致させるもので、使用パルス幅よりも
十分に狭い幅でなければならない。使用パルス幅が 2μs とすれば黒点信号の時間幅は直感的に 0.5μs よりも小さいだろう!
高周波の配線同様の配慮をした技法が必要である。
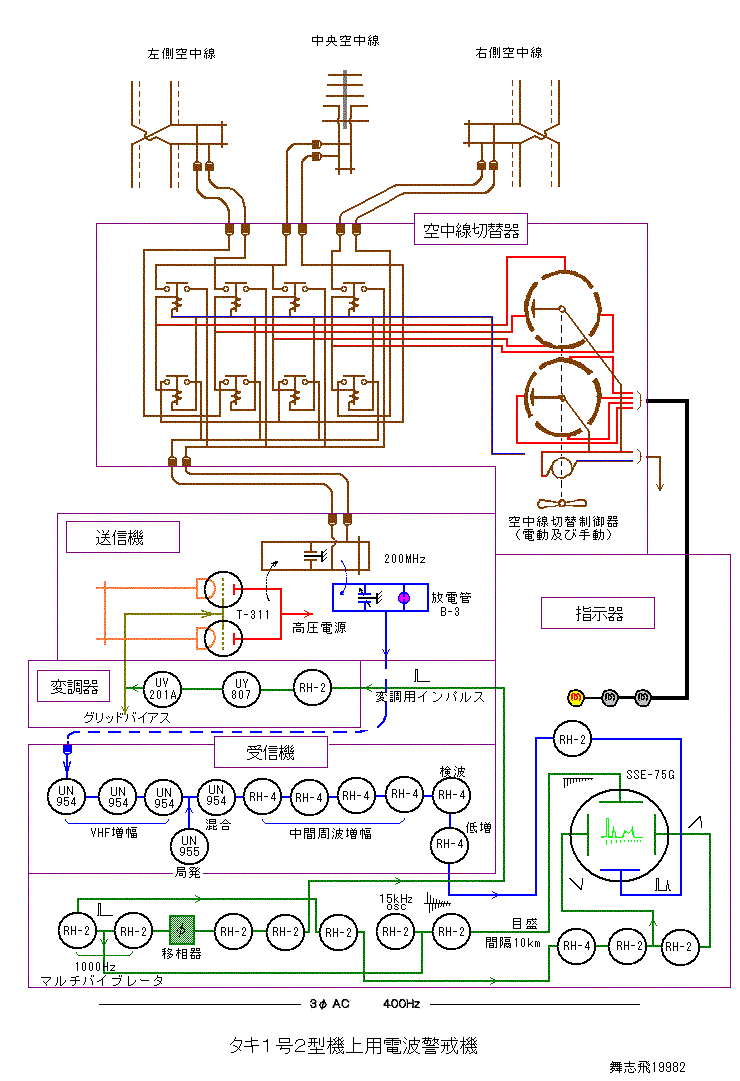
米英、独は実戦に投入していたが、我が陸軍、海軍は、VHFの200MHzから上とUHF全域が空白。
真空管の技術が及ばなかったのが主因。次の数種が漸く生産に懸かる段階だった。
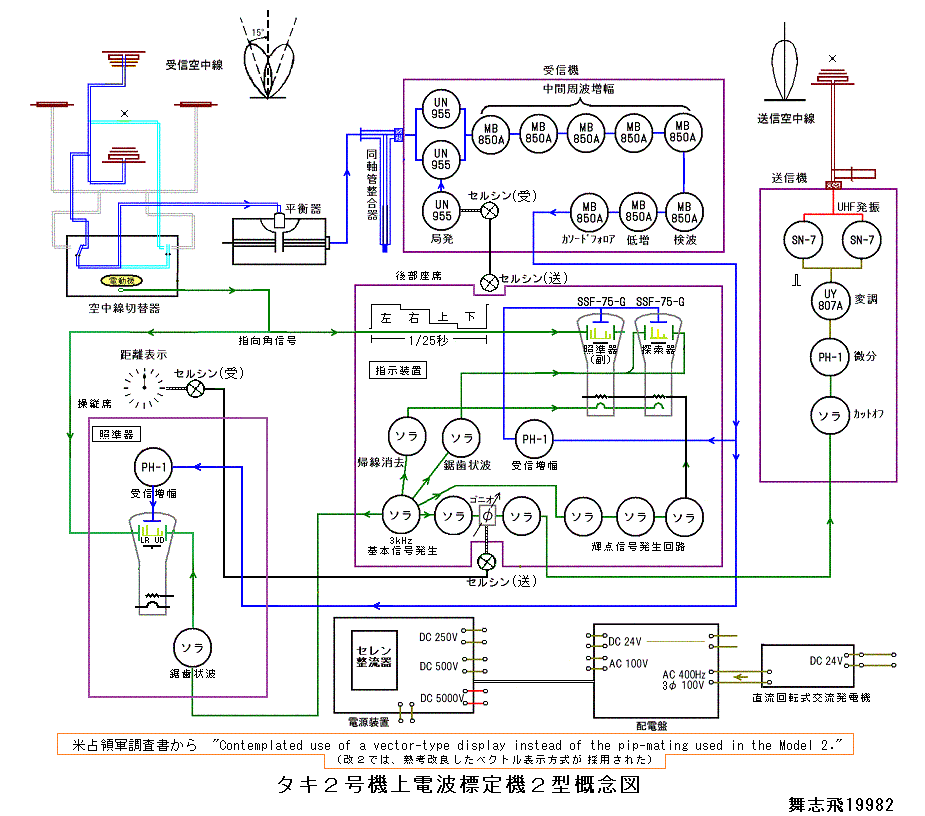
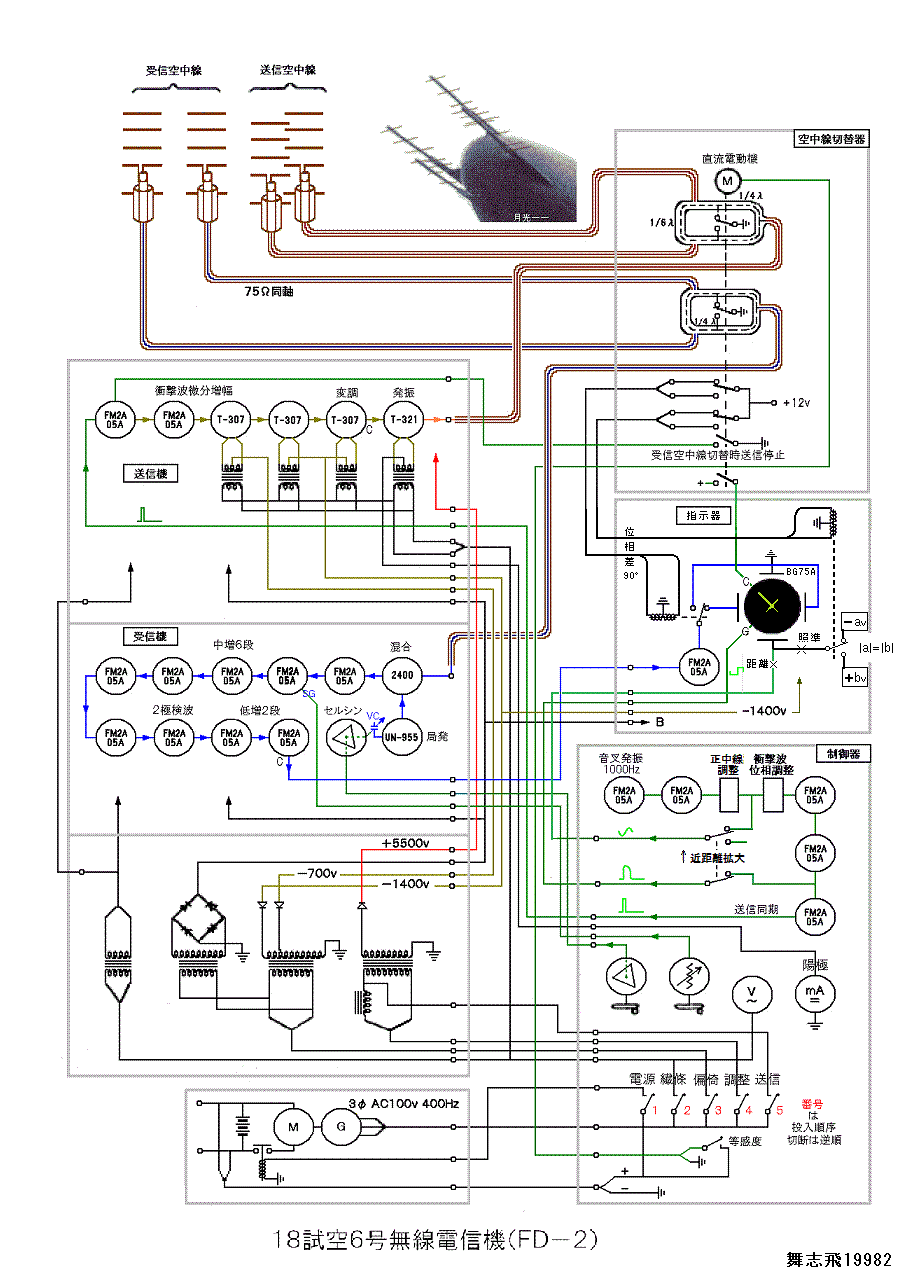
指示器は『索敵』と『照準』を兼用しているが、照準では距離走査を上下角表示に切り替え、照準操縦を容易にしている。
これが占領米軍に興味を持たれたらしく、本機種の調査は特に綿密で紙数が多く費やされている。
表示方法、巧妙な回路でベクトルもどきを達成していた!
◆ ◆
送信アンテナが上・下に 受信アンテナが右・左に それぞれ、等感度方式対応移相差を与えて菱形に配置されている。
受信アンテナ(右)と隣接する直角配置の送信アンテナ(下)、次に受信アンテナ(左)、次に送信アンテナ(上)、
と2組ずつを組ませてコニカルスキャンを行っている。
つまり、4個のアンテナの2個ずつの組み合わせを順々に組み替えて、90°ステップで(指向角を)回転させている。
観測装置をこの回転に同期して切り替えれば、送信指向性と受信指向性が合成されて、X字状に放射した大小4個によって
ベクトルもどきを表示する。その指向最大を追って接敵する。
選択機能不要
① 操縦員は機長であるから、他から攻撃目標を指示すれば指揮命令系統が分裂する。
② λ=60cmは指向性が十分で自己選択は可能!
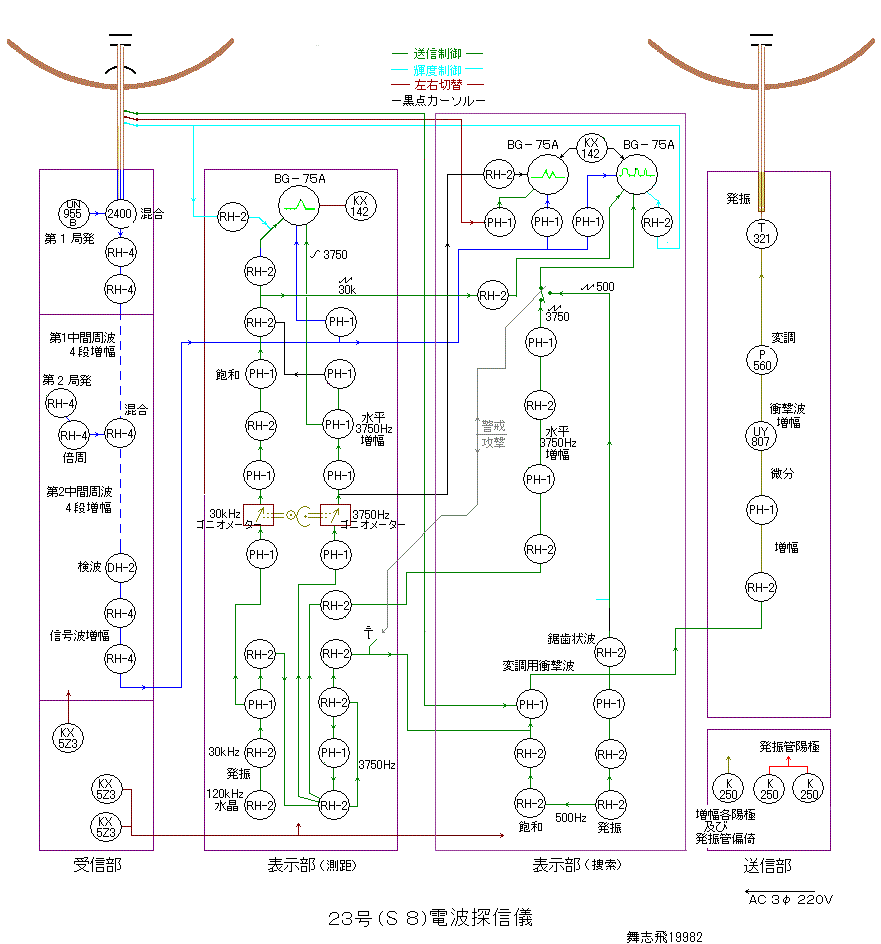
垂直偏波給電のパラボラアンテナが2個上下に接して配置されている写真を見ましたが、
私が目撃したものは2個を左右に引き離して取り付けられていました。42号電探用の回転桁に仮設したものでした。概要図も左右配置です。
進化途上実験を重ねていたので次々に変化して呼称が同じでも形態が異なっていたものと思います。
第2中間周波でスタガー式を採用し、測距機構がウルツブルグ形式であるのはウルツブルグ型に改装の途中段階と思いましたが、
或いは対水上時に既にウルツ方式を導入していたのでしょうか?
果たしてどうかを調べてみました。
Target Report-Japanese Submarine and Shipborne Rader の総括表記載
23(s8) の項では繰替周波数=3750Hz 測距精度=±50m
Target Report-Japanese Land-Based Rader の総括表記載
s8A の項では繰替周波数=3750Hz 測距精度=±50m
両方同じです。このことから、対空射撃用に改造する以前から測距にウルツブルグ方式が採用されていたことを確認しました。
掲載のイラストは昭和20年3月25日(日)見学の記憶を後日描いたものです。
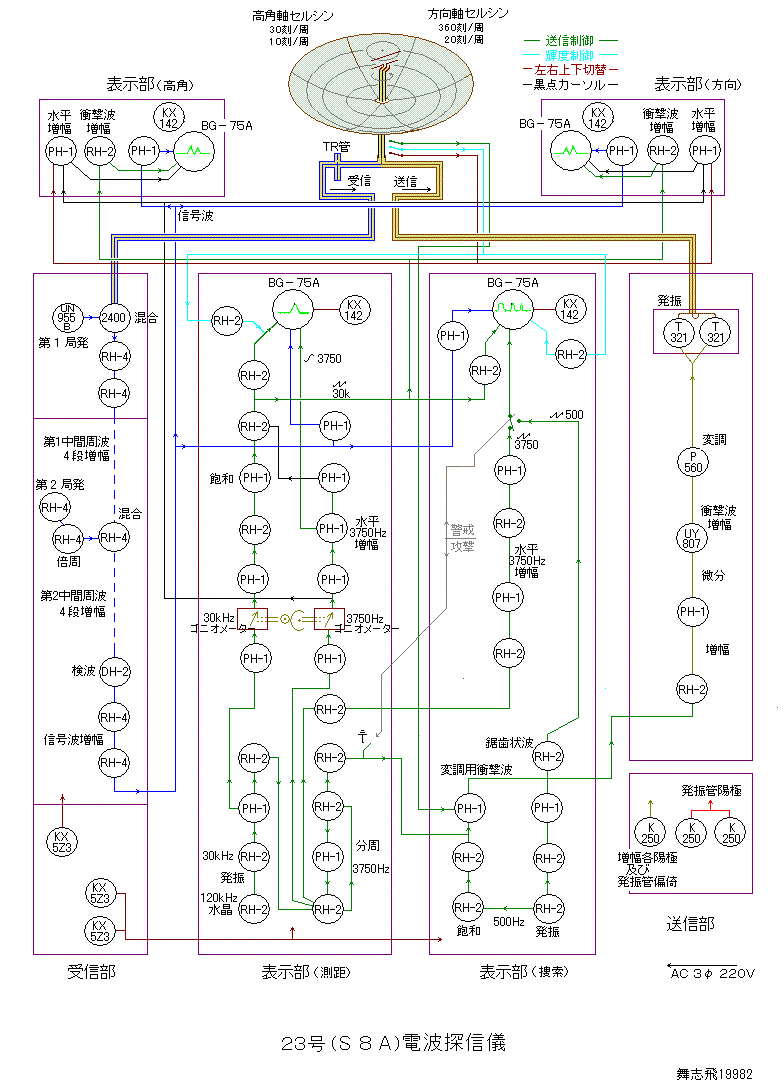
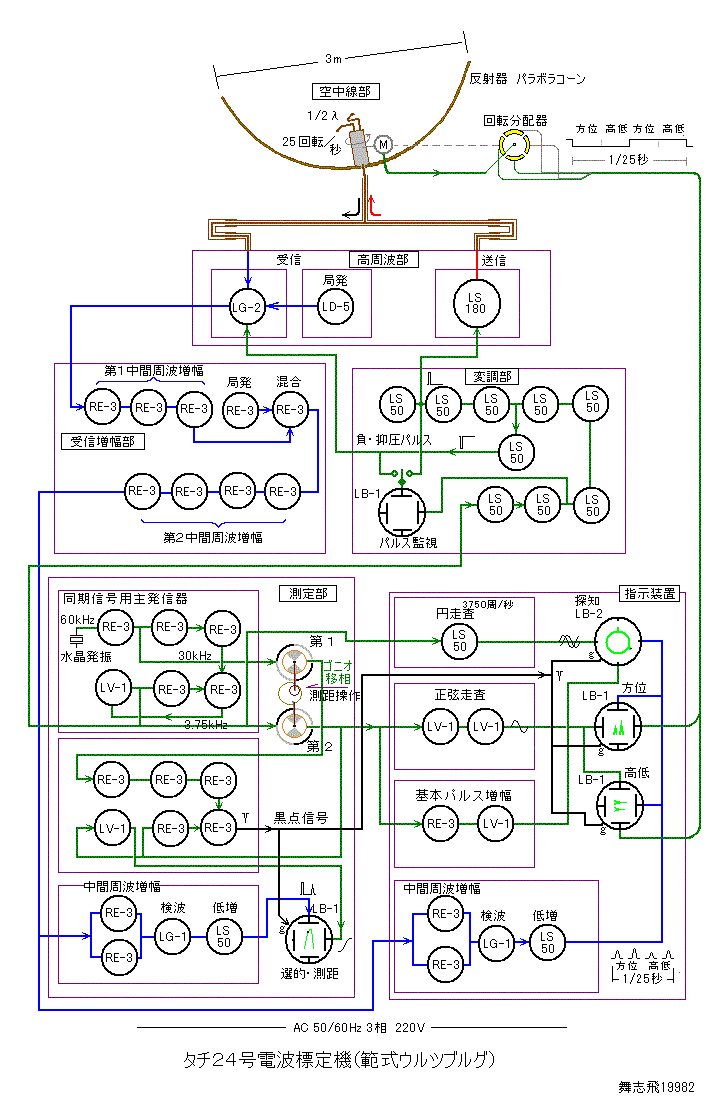
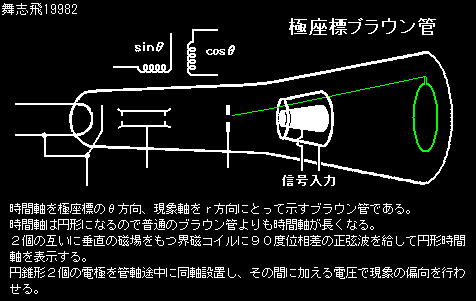
SHFの下、『UHFの上半部』は有効さは分かっても閑散、
人影稀な荒野の様、戦後半導体技術の進展に伴って負性抵抗が便利になり充実した!
その『UHFの上半部』に限界挑戦機、タキ14号!
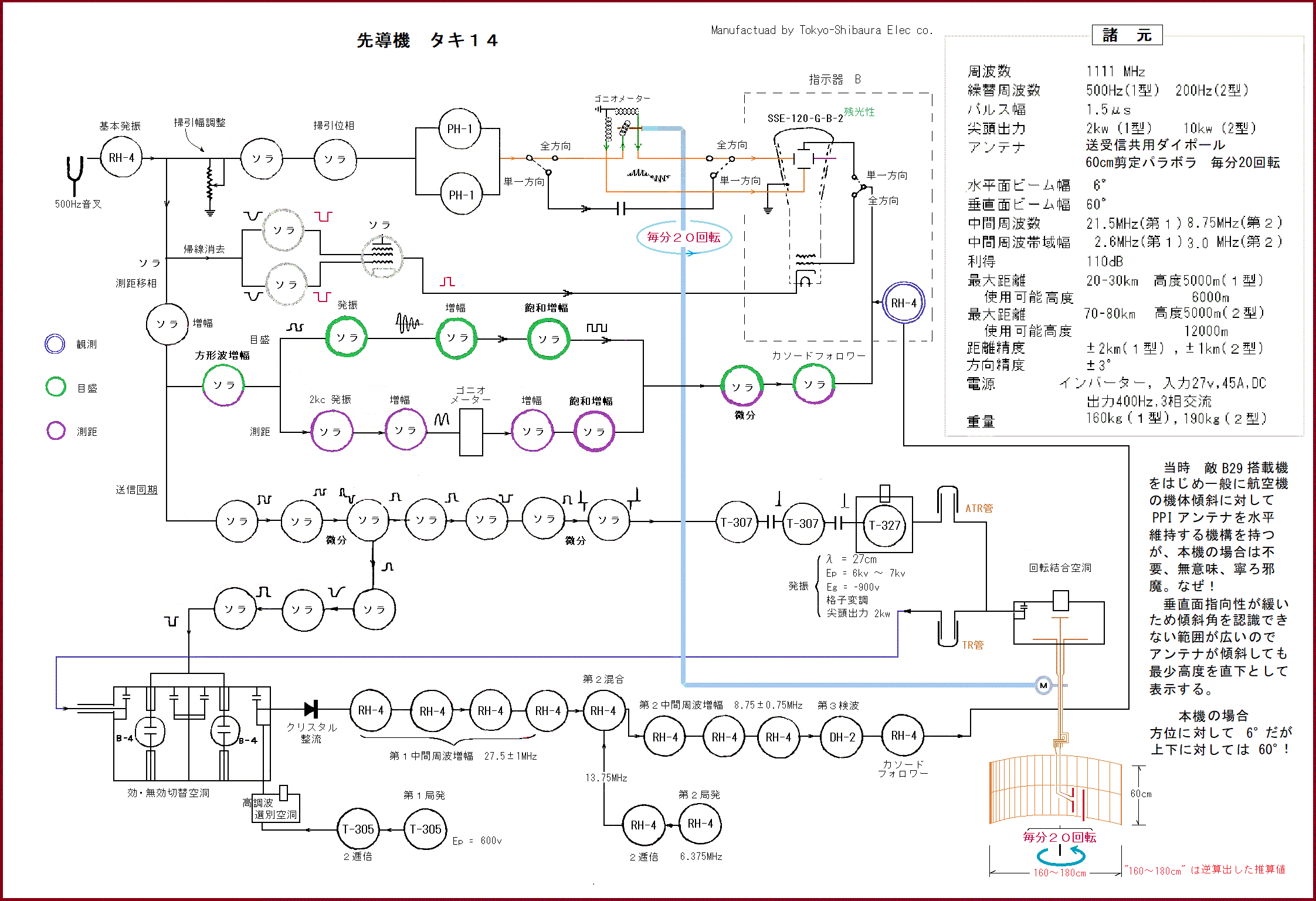
The antenna system consisted of a clipped of a 60cm. parabola with a dipole and a group
of directors in front. The resulting beam was to be 6 degrees wide (horizontally) and 60
degrees (vertically). It was to be mounted in a radome beneath the fuselage. No provision was wide for tilting the antenna since the vertical beam width was so luggage.
アンテナシステムは60cmの切抜き部分で構成され、パラボラとダイポールの合成ビーム幅は、水平方向に 6 度 、 垂直方向に 60 度であった。
アンテナは胴体の下にレドームを設けて収容する運びだった。
垂直方向のビーム幅が非常に大きかったため、アンテナを傾けるための準備はなかった。
以上は拙者意訳
レーダー先進の米軍は更に、『持てる国』の故に貧乏国の知恵に及ばなかった例をほかにも幾つか見つけた!
米軍 SCR-268 は変調にコストをかけて大きな迂回をしている! 我が海軍の41号電探(S3)は外観からそれの模倣とされながら、
内容では無駄を省く知恵が多く働いていた!
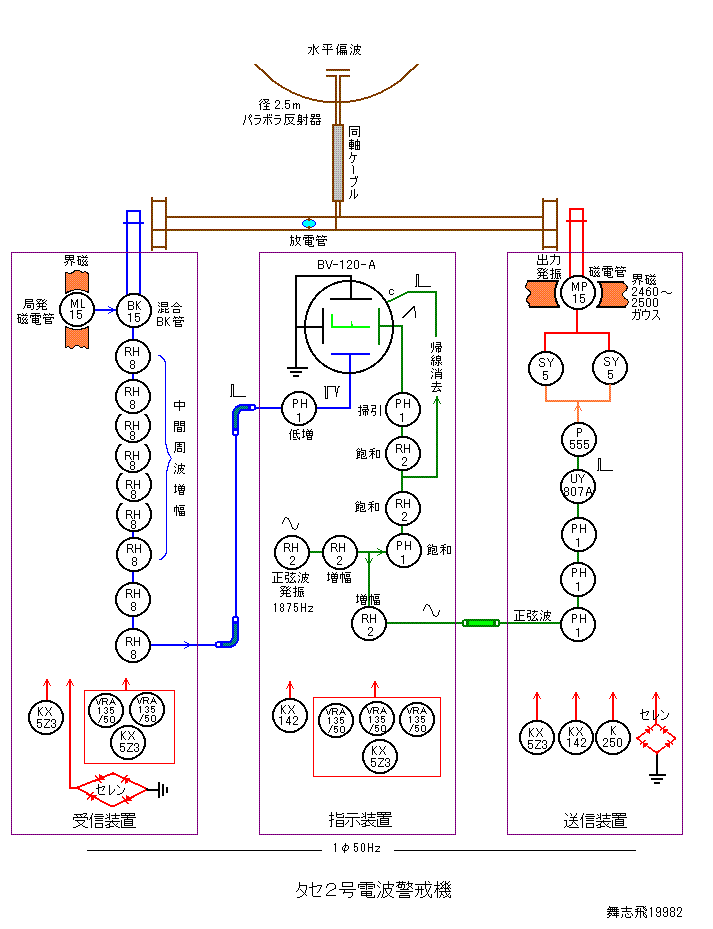
直線的に「200分の1秒間に 30 MHz 変化する」とあるので、秒当りの周波数勾配は
30 × 106 ΔHz/s × 200 = 6 × 109 ΔHz/s ・・・・(1)------ 電波速度 ------ 3 × 108 m/s ・・・・・(2)
(2) ÷ (1) = 0.05 m/ΔHz ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)
電波走行距離は高度の往復である
∴ 1 Hz当りの高度勾配は (3) ÷ 2 = 0.025 m/ΔHz送信波と大地反射波の周波数差(絶対値)は
高度 1 m 当り 40 Hz となり 相当する周波数のビートが生じる。
これを高度目盛に書き換えた周波計で直読する。
この機種での周波計の仕組みは、ビートを低周波増幅してC 回路を切り替える。
C は定電圧箇所から一定電荷を受取って蓄積したものを下流に放出する。
C は周期ごとに定量の電荷をリレーするので平均電流は周波数に比例する。
――バケツに1杯ずつ汲んで流すようなもの。流量は回数に比例する――
これでDC電流計を振らせて換算した目盛で高度を読み取る。
右図を電子回路化したものが用いられた。
なぜ『UHFの対数的上半部』を通り越してSHFが先に実用が進んだか?
それは、磁電管など、電子群の速度を操るに大きさが手ごろだっただから!
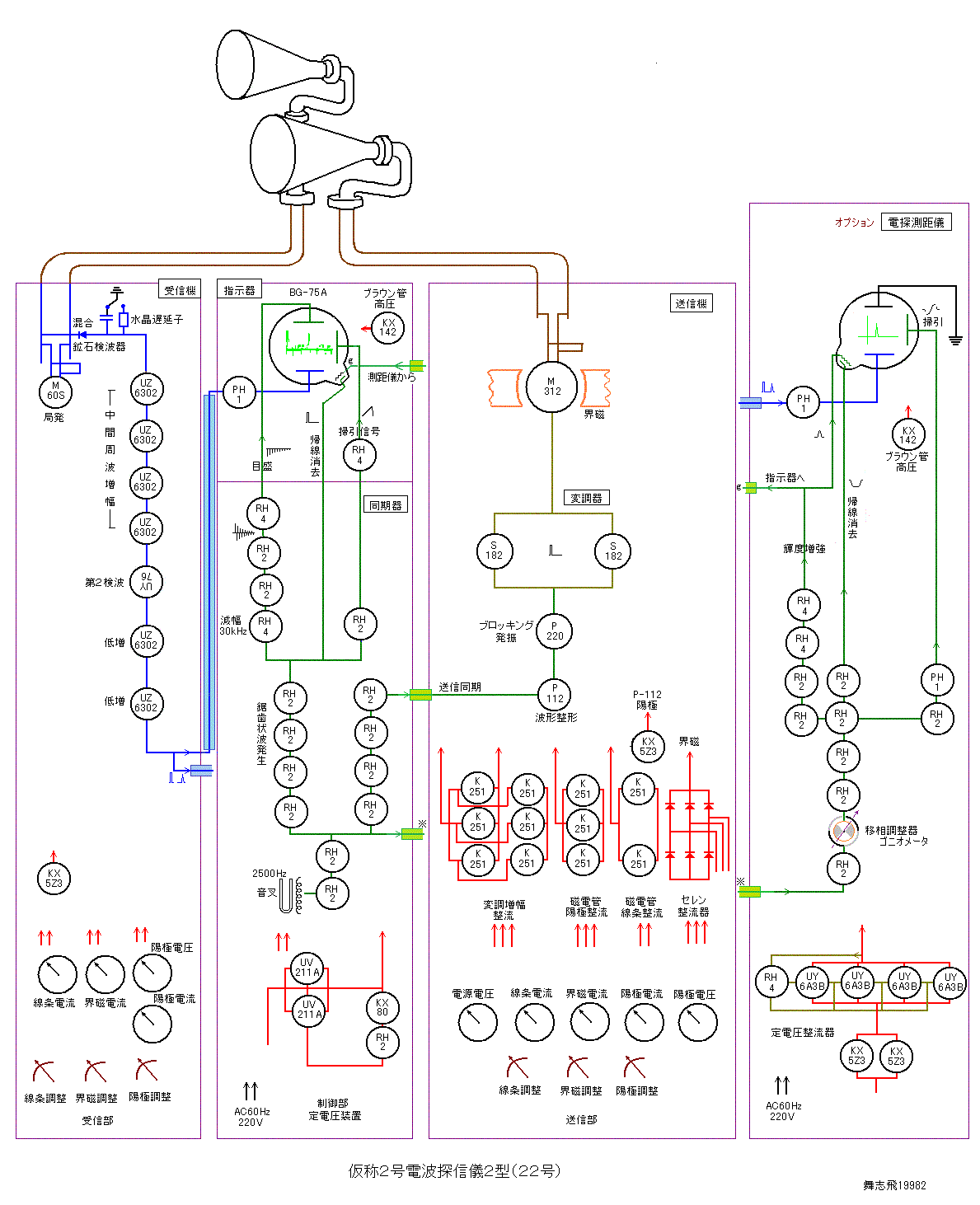
マイクロ波電探は変調パワーが大きい、陽極変調だから!
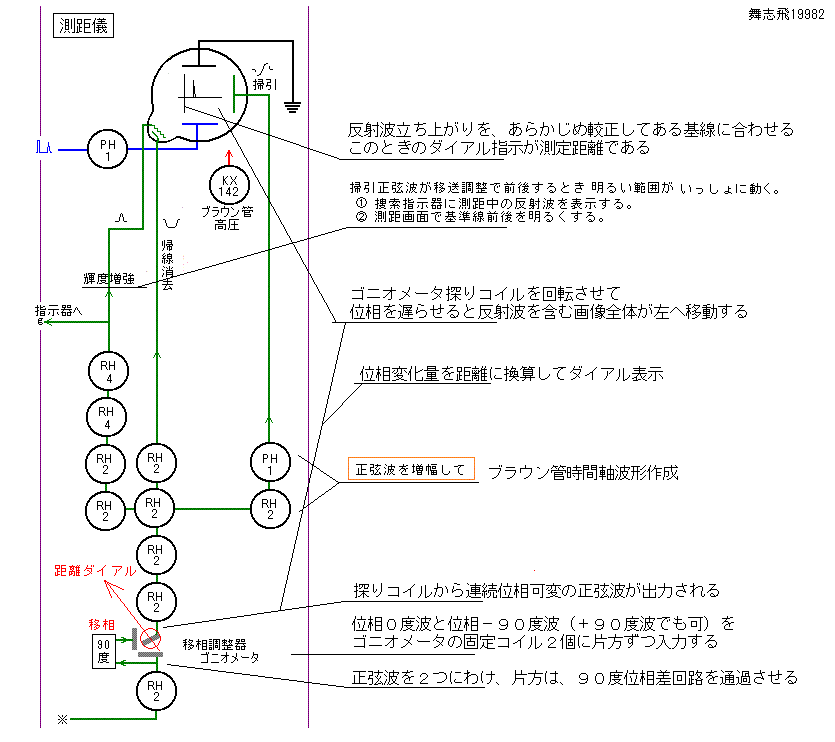
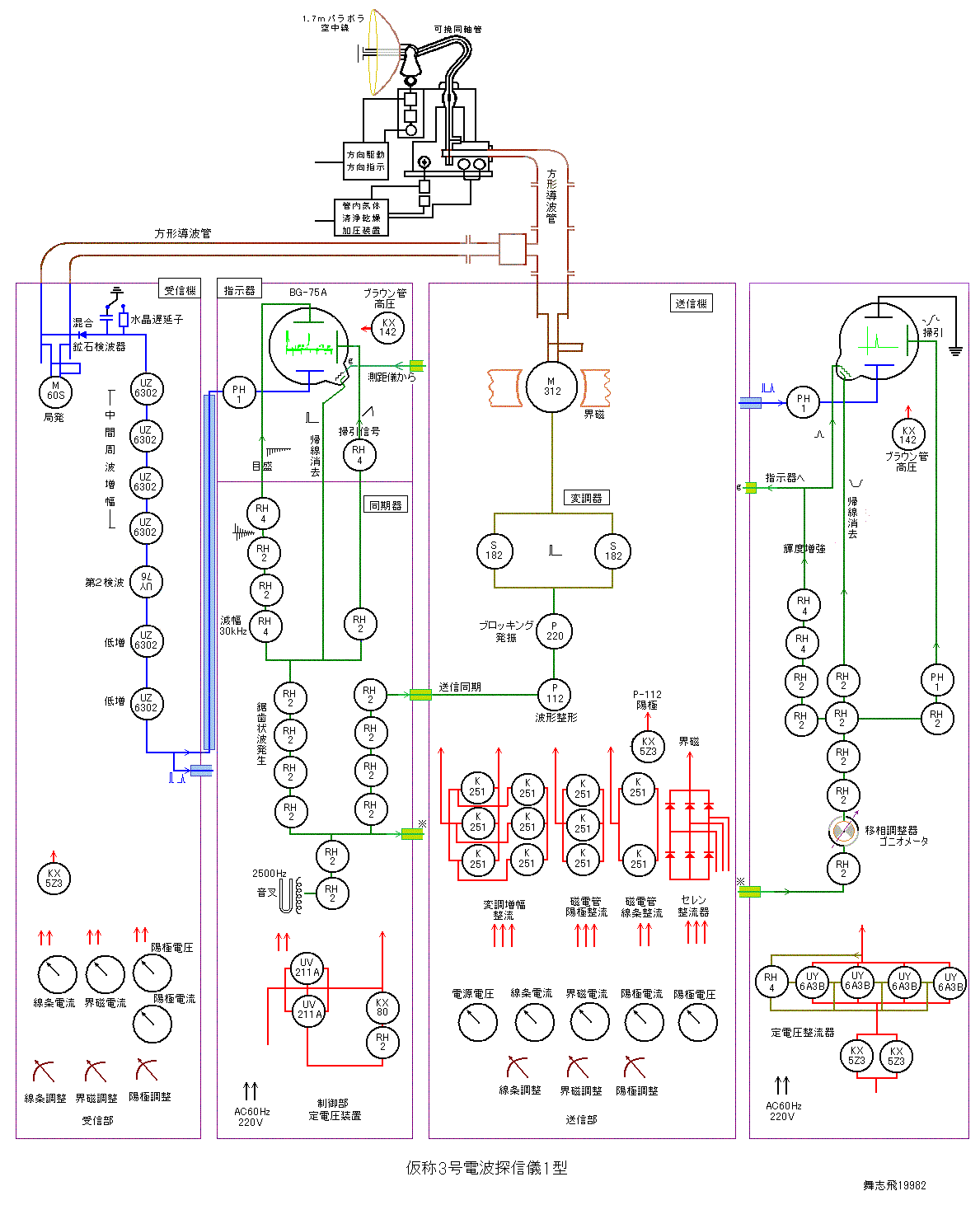
3号1型は、3号2型が重量、容積大で、非現実的であるとの非難に対し、2号3型に使用した架台並びに反射鏡を使用し、導波管を架台内部に納め、
本体は同軸ケーブルを用いて接続し、空中線装置のみを回転する方式のものである。(FatherさんのHPから失敬!)
UHF用のパラボラをSHFに転用することは、メッシュの密度と放物面精度が適用限界内ならば輻射部分を交換して可能。