


◎ 閑
小田急電車の走る音が 束の間の平和を感じさせる
闇にこだましながら 兵舎をよぎってゆく
空襲無し 天候穏やか 夜までが長い 鬼班長は上陸
◎温習

◎手旗信号
◎春の兆し
厳寒時、早朝1万メートル駆け足。総員起しの時刻繰り上げ、
20個分隊は各々『分隊旗』を先頭に掲げて足並みをそろえて走る。
どのくらいか期間は覚えていなかったが、連日だった。
この訓練もあと1日か2日の頃、隊伍の中から誰かが「梅が咲いている」と叫んだのがいた。
香りも漂っていた。生垣越しに民家の庭に咲いているのを気が付いていたけれども、
息を継ぐのが精一杯で声を出せる余裕はなかった。キツイやつもいたものだ!
走り終わって、誰もが待ち遠しかった春の兆しを娑婆で見つけて、ほっとした! 一瞬。
【海軍数字旗】
◎タコ壷
実習場とは言いながら13号アンテナ1基に1つずつタコ壷が掘られていた。
覗いてみると崩れて浅くなっている、それにしても中にしゃがめば空が見えるだけ。
これが俺の墓穴になるかもしれない!
近くに咲いていた野の花を、穴のふちへ移植した。
別なアンテナのタコ壷を見たら同じように花が咲いている。
誰か知らないが俺と同じ思いの奴がいた。 (s20/5)
◎戦記文学のウソ
太平洋戦争の戦記物にレーダが登場するものを、古書店で立ち読みで探していたところ
「迫りくる敵艦載機4機をわが艦上レーダが捕らえた」と言う意味の記載があった。
この記事はウソか、間違いかだ!
編隊らしいと分かっても機数は分かるはずがない。
単機か編隊か小型機か大型機かの判別は観測した電測員の推定である。
推定するための基準などは無い。
距離が近いのに感度が小さい、逆に遠いのに感度が大きいとか、反射波の距離幅が狭く
針のようだったりその逆であったり、またフェーディングの深浅などを総合勘案したも
ので、断定を避けて「らしきもの」と報告するのである。
練習生が実習でこれは小型機単機だ、これは大型機編隊だと判定訓練をして、たまた
まそれが頭上付近を通過した場合判定の正否が分かるといった経験によるものである。
4機という数はレーダで発見した時点でなく、接近して眼鏡或いは目視できたときに
始めて分かったはずだ。
◎談合・八百長
「回れ 押せ〜」甲板掃除途中の号令である。
横1列に並んで水に浸したソーフ(雑布、ロープの屑をほぐした物)を両手に持って
走って甲板(船でなくとも床はすべて甲板)を磨く。
遅いのが集められてしごかれる。しごかれるのが怖いから全力で押す。
やがて、速く走れる要領を自然に会得するが、秘密にして誰にも教えない。
ある時談合、「遅い者にあわせて横一線に最後まで揃って押そうじゃないか」
「力を出し切っていないと気合をかけられるぞ」
「みんなが、一番遅い者にあわせて、全力の格好で押せばよい」
つぎに、個人個人が秘密にしていた要領を出し合った。
そして、
八百長・・・ その結果
「よし!」「気がそろっていてよろしい」「団結心がついてきた!」
その後、この甲板掃除で気合が入れられることがなかった。
経験的で文字になっていない【指導要領】の成果に、班長たちは満足だった・・・。
◎教育設備
海軍の部隊でありながらも「学校」というからには教育の場所である。
教官・教員は揃えられた。教えられるほうも俺たち同期練習生が全国から3000名集められた。教室(講堂)も建てられ、それらしく黒板・教卓が据えられ、教材も各室ごとに電波探信儀1組(アンテナも含めて)が置かれていた。教科書・ノート・文房具なども渡された。(但し赤本は授業後回収) 校外実習場も完備された。
けれども学校と言いば小学校から何々学校まで必ずある物が、電測学校の俺たちには無かった
はて 何だと思いますか? 「暖房装置!」 それも無かったが、・・・
今考えれば驚き!内地ではあるけれども全く暖房設備が無いところで一冬を過ごした。
・・・もっと大事なものとうとう卒業まで間に合わなかった。
俺たちより後から来たのに学生の所にはあった。差別されたのか、少数だから間に合ったのか? (s20/5/31)学校にあるはずなのに無かったものとは『なに』でしょう?
某元大学教授が返事を下さった 『 机・・ということはないでしょうねえ。』◇正解 机です。筆記やテストのときは銘々に渡されている手箱と称する木製の日用品箱を机の代用にして床に座って書きました。
温習(自習)や答案作成などは食卓を代用しますが、座学(講義)は机なしで、メモを取るのが不自由でした。
◎服装違反
号令「作業員整列!」自由時間でその号令を聞いたら素早く駆け付けなければならない。
用務が予想できることもあるが何をさせられるのか? そんな思惑で躊躇逡巡の間はない。
そのときは、長後駅貨物ホームから炊事用の薪運び作業だった。1把(3.75kg)ずつ担いで帰る。内外合計往復6km
2〜30人で往復駆け足。指揮する班長も担いだ。度々のことなので予想の通りだった! が、
私1人が服装違反のゴム草履履きのまま隊伍を組んで正門を出て行進は駆け足に変わった。
私の位置は2列縦隊の右列にいたが左隣の者が「班長に見つかるとヤバい俺と交代しろ」と目立たない位置に私を隠そうと声をかけてきた。
全く忘れていた!ハッと気付いて私自身恐ろしくなって、駆け足しながら前後の者たちと息を合わせながら従った。
班長から見つかればまずいし、一般住民に見られてもよくない。
位置が入れ替わって足並みと隊伍が整え終わったったころ。指揮者である田中一曹が歩調を合わせたまま近寄ってきた。
みんながひやひやの思い! 「いいの履いてるな!」・・・・・班長は既に俺たちの行動を知っていたらしい!
周囲の者たちに「街中で気合をかけるわけにいいかないから帰ってからやられるぞ」なにしろ新編成の班で班長の気質はわからない!
「貴様のせいで全体責任だ! と、全員がやられる」などと言われながら駆けた。
どうしてこんな事態になったか、
「作業員整列、兵舎前」の号令で、艦内靴(デッキシューズ)を履いて兵舎から飛び出す。私はたまたまゴム草履をはいて外にいた。
履きかいる暇はない。「ここまで」と所要人員で打ち切られて罰直が課せられる中には入りたくない。ゴム草履のまま整列に加わった。
ゴム草履 学徒動員海軍航空技術廠で支給されたもので耐久性が重視された簡易な履物だった。
入隊後私物として利用して、夜間厠或いは洗面所に行くとき履いた。勿論「総員起こし」後は履かない。
古靴を加工してスリッパにして利用していたものもいたが、チョイとだからと艦内靴の踵を踏みつけて突っかけている奴は嫌いだ!【平和な今もいる】
その頃、「総員起こし5分前」と同時に発令の「作業員整列」は、まだ夜が明けきっていない時刻だった。暗いままならば何のこともなかったのだが!
しかし私は怒られずに済むと直感した。
班長にもミスがあった。「整列」の目的は、指揮者は整列させて一目で点検し、欠陥あるものを発見する。
褒められる点もある。その頃盛んに鍛えられていた共同精神が発揮されている!
班長自身も衛兵所の前を通るとき気がかりだったのでは!
衛兵所は出るとき見逃した。帰りは故意にも見逃す・・・ やはり無事通過!!
予想通り制裁も罰直もなかった。
◎教育設備−2
軍の部隊には、藁(わら)人形が数体並べて立てられていた。演習で突撃の終わりに銃剣で突き刺す相手だ。電測学校にはこれが無かった。
新兵教育中の或る日、陸戦の課業で木銃を担いで近くの日本大学農学部へ行った。大学には人影は見えなかった。
吉田上等兵曹指揮のもと我ら第1分隊150名は無断で構内に入り、遠慮なく自分たちの練兵場のようにして、木銃を構え、そこに並んでいる藁人形に突き当たった。突く勢いがこもっていないと、善行章3本の吉田上曹に何回もやりなおさせられる。
数十メートル戻ったところに再び伏せて、また突撃!
こうして全員一巡すると、器用な者や力持ちが何人か指名されて途中農家からもらってきた稲藁で修復する。吉田上曹はすごく器用な方だったので元以上に直る。そして隊伍を整えて帰隊した。
人殺しの稽古をする設備が私立大学にあって、軍の部隊にそれが無かった! どうして? (s19/12)
◎器具室2題
鍛えられている 当人 は閑どころではないが先輩たちの恰好の暇つぶし!
右図のT-311は上部端子2個間 即ち、陽極と格子間に直流1万ボルト(+8800v、-1200v)の電圧がかけられた。
トランスはAC7000vだが整流後DC8800vになる。話題1
13号送信機のスイッチは回転式で4段ステップになっていた。線条⇔偏倚⇔調整⇔送信
実機に触る前に座学で「電源投入は線条を入れたら30秒以上経ってからつぎの偏倚に投入すること」と繰返し教えられた。
最初の実習は教班長が立ち上げから調整・観測・測定・終了まで説明しながらやって見せた。
次の実習の時「他用を終わらして行くから、おまえたちでできるところまででやっててよろしい」ということで教員不在で始まった。誰も手を出さないので、私がスイッチを入れた。先ず線条そして30秒以上経ったところで偏倚に入れ続いて調整にした。 「バッチン」!! 過負荷継電器が動作して電源が落ちた。 再投入してみたら送信管Tー311が2個とも線条が点かない。教えられた通りやって、なにも手順に誤りはなかったはずだ。
手を出さなかった者たちが私に「お前の責任だ。どうする、どうする!」とざわめき出す。『誰か任せ』で手を出さなかったくせに。誰も手を出さずに時間を過ごしたら全員がどんなに気合いを入れられたことか?
私は1人で教員室へ申告に行く心算になった時、伍長 大上が立ちあがり一緒に行こうと言ってくれた。
『伍長』 海軍で伍長とは等級ではなく同列の中から選ばれて任命された役。いわば級長
二等兵の伍長もいたし上等兵曹の伍長もいた。
教員室へ行ったら私たちの教班長は居なくて他の教員たちに
「お前貯金はいくら持ってる?」
「30円余りあります」
「おまえは?」
「同じく30円ほどです」
「1人30円か お前の班全員で千円集めたとして、足りないなあ!」
「いいよ心配するな俺がこれを売って弁償してやる。これを1 個売ればそれの何本分にもなるぞ」
「こういうのもあるぞ!これなんかそれのまた何十本分もするんだぞ」
無責任の先輩たちは教材標本のブラウン管だの磁電管(マグネトロン)だのを引っ張り出して私たち2人をなぶって喜んでいる。 自分等の班長が留守だとこうなる!
教材は教員室の衣嚢棚が保管場所にされていた。これらは廃品中、外見がよいものから選んだのだろう!
そのうち、教班長のうち一番後任の 松井二曹が不良真空管を新品と交換する手続きを教えてくれた。
!手取り足取り!
早速、「松井」の印鑑を預かり、大上と2人で器具室へ行ってTー311 2個の交換を受けてきた。勘ぐれば、俺たちの教班長は俺たちを験そうとして仕掛けたのでは? 切れている送信管を取付けて・・・
俺たちの教班長はそういうやり方の方だった。【教班長田中一曹、数年後日本国籍を手放された。】
もっと実習を積んだ後ならば線条の光が隙間から見えないので気付く。更にTー3112個とも陽極電流が流れなければ、無負荷だから放電開始までリアクトルは効かない。
尖頭値は7000ボルト×√2=9900ボルトまで上昇充電する。バイアスの−1300ボルトが加わり冷真空管のP・G間11200ボルトが放電、続いて空隙避雷器放電、最後に過負荷継電器を遮断させ、一連の保護回路は完全動作したことが推理できる!
仮に余熱時間不足が原因としてもT-311が2個とも線条断心することは考えられない。線条が両方断心しているところに陽極加圧したら、上述の現象は発生して当然である!無責任の先輩たちは教材標本のブラウン管だの磁電管だのを引っ張り出して私たち2人をなぶって喜んでいた。
「ご好意は有難いのですが、それを売ったら 2度と娑婆の土が踏めなくなりますよ」 と、お返しすればよかった・・・そこまで脳みそが回転せず後々悔やむ・・・!
なぶられた・からかわれたと思ったのは間違いかもしれない。
私たち2人に磁電管・ブラウン管・送信管の価格の如何なるものかを教えて下さろうとの心遣いだったとしたら、ご好意を気付かず申し訳ありませんでした。
真空管など不良になった部品は器具室へ行って新品と交換する。器具室には『うるさい』水兵が任されて控えている。
このような性格を適任者として主計科が委嘱したのだろう。
或る日、担任でない教員に T−307
という変調用の真空管4個を器具室へ行って交換してくるように命じられた。この役、敬遠されて要領のへたな私がやることになったようだ。
器具室が『うるさい』のを知っていたから、教員の氏名をしつこく伺って印鑑を預かり手落ち無く万全のつもりで出かけた。
器具室で用紙の欄を全部書き込んで捺印して提出、
すんなり交換してもらえると思っていたら、「どの真空管がどのように不良なのだ?
分からなければ班長に聞いて来い。そうでなければ交換できない」と、
「 2 個が断心で 2 個が機能低下です」と答えたが「それではだめだ、1つづつ個別に言え」と言う。
では「そこにあるテスター貸してください」と言ったら
「貸すことはできない戻って山木一曹に聞いてこないうちはダメだ」と
そうか分かったとその場を引いた。しかし戻って出なおすわけにはいかない。用が足りなくて戻ったなど言えるものか、「たるんでいる」と気合を入れられるだろう。第1あんな遠くまで往復するそんな時間も無い。
テスターなど借りなくても導通試験の方法などいくらでもある!
ちょっと先の講堂の脇に配電函を見つけた。表示灯のネオン管を外して、それで
4 個の真空管のヒーター線の導通試験をした。2個の断心が個別に分かった。それで再び器具室へ行って
「これとこれは断心、これとこれは機能低下」と言って差し出した。件の係員テスターで導通を調べながら訝しい顔で
「班長に聞いてきたのか?」と聞くから
「はい」と答えた。早過ぎると思ったのだろう、班に帰って、どやされてそれからショボショボ来るだろうと思っていたに違いない。
奥で帳簿をイジっている器具室先任下士にも聞こえるように音量を上げて、「機能低下にも色々あるので、説明します」と、始めようとしたら、
態度も言葉も変わって新品を 4 個渡されたので受け取って帰った。待っていた山木教員は
「すんなり交換してくれたか」、
「ゴタゴタ言われました」
「それでどうした」
同僚一同を見まわしながら、
「なめかえしました」
とだけ答えた。
彼の器具室の窓口係は嘗て山木教員にしごかれた ことがあるのかもしれない。
前に、送信管を2個交換したことがあった。その時は2個とも同じ断心だったので問題無かった。個々に不良情況の記録が必要とは思わなかった。


実習場なか程の芝生に20〜30人集まって何かしている。
近づいてみると1人の教員を中心にして、一度ばらばらにした13号電探のアンテナを始めから組み立てている。
更に近寄ると「お前らの来るところではない」と追い払われた。俺たちを遠ざけて違うことを習っている。
俺たちは、アンテナ素子が組まれている8メートルの三角柱を垂直に立てる実習だけだった。
あのような輻射器、反射器、更にその支持棒までの取付けは、全くやらなかった。
また、アンテナを立てたり倒したりを繰り返して、チームワークの修練もしていたようだ。
機械科出身など分隊を越えて電気オンチを集めた特訓で、配属先で![]() が泣かないようにとのご親切!
が泣かないようにとのご親切!
卒業した配置先で新しくアンテナを立てるとき、彼らが指揮すれば不体裁な烏合の衆にはならないだろう!
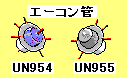 不寝番という眠くて辛い当番がまわってくる。立直中のいろいろな責任事項があった。150名の仲間たちのうち、寝相が悪いのを見付けて風邪を引かないよう直してやることも仕事だった。交代時間になって引き継ぎを終やすとホッとする。
不寝番という眠くて辛い当番がまわってくる。立直中のいろいろな責任事項があった。150名の仲間たちのうち、寝相が悪いのを見付けて風邪を引かないよう直してやることも仕事だった。交代時間になって引き継ぎを終やすとホッとする。
私が不寝番のとき、眠りながら、もがいている者がいた。
寝返りしてよけた寝床の上にエーコン管が3個か4個転がっていた。
・・・すぐ察しが付いた!
どこかから盗んだか、拾ったかしてきて、隠し切れなくて抱いて寝た。それが背中に回って、痛くてたまらず寝返りしていたのだった。
5本或いは7本の電極が角(つの)のように突き出ている。さぞ、痛かっただろう。ばかもん。自業自得だ!
不思議にもその角が曲がっている。寝具と背中の間にはさまれたくらいで曲がるわけがない。それ程強く押されたら皮膚を破って肉か骨に突き刺さる筈だ。
「どうした、これ!」と言ったらやっと目を覚まして拾い集めて慌てて腹のほうへ隠した。そして顔をしかめて拝まれた。
翌日、彼の行動に注目していた。 ・・・こっそり不要兵器の解体現場へ返しに行き来するのを、こっそり見守った。
(s20/4)
号令の「マテ」は陸軍には無かっただろう!
海軍では、「マテ」の号令がラッパや音声で下令される。
陸軍の「撃ち方マテ」の号令は海軍でも陸戦で使う。これとは違う。
「マテ」がかかるとそのままの姿勢で動いてはいけない。
号令に従って皆が止まるから1人だけ動けば、すぐに見つかってどやされる。
どやすほうも号令に従っているので後で「マテ」が解除されてからだ。「マテ」の解除は「カカレ」で、
これも声又はラッパで号令される。なれないうちは苦労する。
歩行中片足を踏み出すときに「マテ」がかかったら、その片足を持ち上げた状態で止まれという、
((フィルムが引っ掛かった活動写真じゃあるまいし))そんなことできるわけがない。
重心は既に前方の未来位置に移っている。しかも慣性を伴っている。
おれ達は物理に合格したからここにいる! 物理学ゼロのお方が考えた号令だろう! それとも
無理を承知でやれと言うのが新兵教育?!
・・・・ それが出来るようになる!
号令を聞き分けるのが速くなるので「まてー」の声が終わる頃には息する塑像になって安定している。
それと、「まて」を教育班長たちは意地悪く新兵に対しては ことさら短く言って鍛えたのだった!
実際はもっと長い! ラッパも「マ・テ〜」と長く聞こえる。
「カカレ」のラッパは「カ・カ・レ〜」と聞こえる。
重量物を持ち上げたときに「マテ」が掛かったたら不運だ! 発令者から
「重量物は静かに下ろせ!」と、追加下令されたこともあったが・・・
全体を一体として緊急徹底するために必要な号令である!! (s19/12)
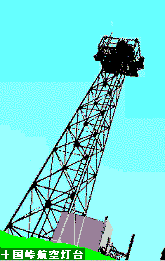 昭和20年4月29日快晴。
昭和20年4月29日快晴。
十国峠行軍。丸腰で助かった。分隊長、分隊士は軍刀を吊っている。ご苦労さま。
「鉄砲持たせりゃ重たがる」空身をよろこぶ・・・上等兵も足軽と同じ!
登りは、山火事の焼け跡に驚きながら1列で山道を登った。
頂上着 皇居遥拝、後 付近自由散策。
売店などは閉まっていても平和時の賑わいが偲ばれた。休止中の航空灯台を見上げた。
ここに電探を据えたら最高に有効だ!電気も来ているし。
箱根路をわが越え来れば伊豆の海やおきの小島に波のよる見ゆ
源実朝さんはよほど眼がよかったようだ! どう目を凝らしても波の寄るのは見えなかった。
芝生の広場に集合して弁当、隠し芸大会。真上をB29が単機で北上、空中写真を撮りに来たのだろう。
帰路はだらだらの舗装道路を隊伍を組んで下る。冬服を着たままで暑さ夏のよう、辛さ無上!
錦ヶ浦の崖上で休憩「ちょっと待て・・・」の自殺警告の立札が目に付いた。
熱海温泉の保養所(海軍借上げの旅館)で行軍終了、全員無事、解散。
(一定距離の行軍を完遂しないと卒業資格かないため休日が兼ねられたのか?)

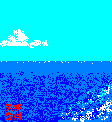 朝礼が終わると20個分隊が一斉に隊列を組んで駆足 兵舎に帰る。各分隊の指揮をするのは当直練習生だ。自分の号令で分隊員150名を手足のように動かさなければならない。駆足だから場面の展開が速い。不適切だと他の分隊と衝突する。大抵の者は自分の当直の朝に雨が降るのを願った。
朝礼が終わると20個分隊が一斉に隊列を組んで駆足 兵舎に帰る。各分隊の指揮をするのは当直練習生だ。自分の号令で分隊員150名を手足のように動かさなければならない。駆足だから場面の展開が速い。不適切だと他の分隊と衝突する。大抵の者は自分の当直の朝に雨が降るのを願った。
練習生期間中に2回当直を経験した者もあったが私は1回だけだった。そして上記のように華々しく指揮をする場面はなかった。
そのかわり、数々の有益体験! 大人になったと自覚した1日だった。
熱海で実習中に当直がまわってきた。練習生は第9、第10の2個分隊だけなので他分隊と衝突することはない。 が、
当直練習生は実習から外れて兵舎の玄関番をする。元はゴルフ場のハウスを海軍が接収して兵舎に使っている。そのフロントで番をしていた。前を教員たちが「衛兵伍長!」と言って冷やかしながら通る。
「にせ衛兵伍長」が「衛兵伍長」らしいことをやらねばならない事態が発生した! (本来衛兵伍長は古参下士官の役だ)
陸軍の将校が馬に乗って従兵に轡を取らせてやって来るのが見えた。
やがて、門前に従兵と馬を待たせて、玄関に入ったので直立して敬礼をした。
「部隊長殿はおられますか」と、入隊以来 ―― 否 生まれてこのかた ―― こんな丁寧な言われ方をしたのは始めてだ。
面食らうとはこのこと。こちら少年兵 相手は、厳めしい姿の陸軍中尉殿!
そして「はて」と思った。
「実習所の所長に御用ですか、それとも私どもの分隊長に御用でしょうか」と聞き返したところ
「最上位の方にお会いしたい」というので、
「どちらも中尉です」と言ってみたけれども「お待ちになってください」といっておいて、3階に駆け上がって報告した。
---- 使ったことも無い言葉「お待ちになってください!」 咄嗟に出たものと我ながら感心する。----
はじめに我らの分隊長が降りてきて話し合っていたが、所長と交代した。
兵舎より更に山を登ったところにある2軒の小屋は、「陸軍のものか海軍のものか」というような話だった。
うちの分隊長が安心したようだった。俺たちのうちの誰かが不都合して
陸さん からねじ込まれたかと思ったにちがいない。
この当直中、階級が7つ、年が十幾つも隔てた陸軍中尉殿から対等の言葉をかけられた。
生まれて初めてのことで些か感動した。大人になったことを自覚した! いわば、あの中尉殿は烏帽子親だ!
(s50/5)
この当直中にもうひとつ「衛兵伍長」役があって失敗談になった。都会出身者ならば起きない失敗。それは
電話に不慣れから起きたしくじり。電話がかかってきて「新田兵曹長を電話口に呼び出してください」と言わたので、取次ぎに行くとき 受話器をフックに掛けた。そうすると電話は切れてしまうことを知らなかった。ハンドルのついている電話機では いつもそうやっていたのに切れたことはなかった! 出身地の町の電話もハンドル付きだった。
新田兵曹長は番号を問い合わせした後に掛けなおした。「うちの兵隊は物事を知らなくて失礼しました・・云々・・」
電話の終わるのをヒヤヒヤ緊張して待っていたら、「受話器をかけると電話が切れてしまうのだぞ」と言っただけで、さっさと3階へ行った。
そして当直の最後に巡検。普通ならばカンテラ、なぜか電測学校は弓張提灯。実習所にはそのどちらも無かった、懐中電灯!
カンテラと違い懐中電灯を向けられると周囲が何も見えない。見当をつけて暗闇に向かって敬礼しながら報告を始めたら「キサマどこへ向かって報告をしているか!」と怒鳴られた。けれども、事情がわかったのだろう「よしっ!」といわれて終わった。
「よしっ!」といったのは当日実習所を巡視にきていた高橋校長で怒鳴ったのは随行した本物の「衛兵伍長」だった。
やはり 少将は上曹より偉い!
うんと辛かったこと、苦しかったこと、悔しかったことは思い出さないことにしている。記憶の底に閉じ込めて浮き上がらないようにしているのだが、軽いものは時たま浮上する。
モールス通信術の訓練がそれだ。
最初はまあまあだったが毎日の受信練習でだんだん字数/分が上げられてくるにつれて、遂に落伍してしまった。
幸い私の班長は砲術科出でモールスを知らない人なので助かった。
分隊全員に通信術を教える隣の班長は通信科あがりで、自分の班の成績を上げようと、自分の班には全員1人ひとりの折れ線グラフを壁に貼ったりして必死だった。それでも私同様の落ちこぼれが1人か2人いた。気合を入れられて、気の毒だった。背中で聞いて身震いがした。
今も耳に残っている、九州方面の地方語か?「イッチョー も トリキラン!」
また白光信号(発光信号と書くのは誤り)があった。
モールス符号によって点滅する光を見て通信文を読み取るのである。これも、思い出したくない訓練光景だ。
(s19/12)
競争心を煽られても、叩かれても、しごかれても、恥ずかしめられても、食事をお預けされても、はたまた涙で説かれて奮起してもオチコボレは立ち直ることはできない!モールス訓練期間が終わって忘れていたが、
卒業を控えた最後の月、2個分隊から20名程呼び出されてモールスの再試験をされた。不合格者救済? ! 「もう忘れてしまった、困った」と思ったが、何回か練習した後にテストして全員合格! 通信速度が緩かった。落第させたら海軍の損失
語調音法は「止めろ」「忘れろ」と言われた。しかし私たちレーダー兵は通信士になるわけでないのだから速成効果のある語調音法(・−・−路上浮浪、−・−・入費超過など)で練習されるべきだった。
教える教員に通信兵からの転換者が多かったので「語調音法では上達に限りがある」と、自分のやってきた専門家養成のやり方で教えた。だから私のように落ちこぼれが多数できる中途半端な成果しか上がらない結果になった。
採用時の通信術適性検査の結果、通信学校と電測学校に振り分けられた。ここにいる大半は上達できないのがわかっていたはず・・・・。
 入隊した最初の1ヵ月は初年兵教育期間で海軍の一般的なことを教育された。その中に『運用』とか『水雷』という科目があった。これらの内容に丸暗記せよと言われたのがいくつもあった。例えば、「救命艇に搭載すべき物品は何々か?」その答えに10品ほどあげれば満点。その答えの1つに『火酒』というのがあった。誰かが「火酒とは何ですか?」と聞いても「字のとおり強い酒だ。海から上げられた生死の境の者に飲ますと生き返るのだ、何でもいいから暗記しろ!」と言われた。ほかの品々は忘れたが『火酒』だけ覚えている。
入隊した最初の1ヵ月は初年兵教育期間で海軍の一般的なことを教育された。その中に『運用』とか『水雷』という科目があった。これらの内容に丸暗記せよと言われたのがいくつもあった。例えば、「救命艇に搭載すべき物品は何々か?」その答えに10品ほどあげれば満点。その答えの1つに『火酒』というのがあった。誰かが「火酒とは何ですか?」と聞いても「字のとおり強い酒だ。海から上げられた生死の境の者に飲ますと生き返るのだ、何でもいいから暗記しろ!」と言われた。ほかの品々は忘れたが『火酒』だけ覚えている。
アルコールが気付薬とは渡来の迷信。麻酔効果を期待したのか? 今、このような使用は許されない。危険です!
水雷にはエンジンで走る魚雷と、敷設した場所で敵を待ち受ける機雷とがある。
機雷の構造は爆発する頭部と、付属の箱があって 水中に投ずると箱が下に沈んで海底に着く。頭部は軽くて浮くように作られている。鎖が延びて、頭部が海底から鎖の長さだけの深さで係留される。機雷には、安全装置がある。
信管は『砂糖』によって安全位置に固定されているが、海中に投じられると砂糖が溶けて位置を移動して安全が解除される。そして敵艦の底が触角を壊すと信管が働いて炸裂する。つまり、海水に投じられないうちは安全、と教わった。
『砂糖』の用途が面白いので覚えている。 「もったいない、塩ではだめなのか?」と私語しあったが誰も質問しなかった。 (s19/12)
陸戦の演習を行うのに小銃が足りなかった。
38式小銃あり、99式(短)小銃あり、銃剣術用の木銃あり、まだまだ足りなくて
伊式小銃というのが使われた。
これはイタリア軍から日本が受注して生産したものだが
イタリヤが降伏して行き場を失ったものだ。
(別の話では日本がイタリヤから輸入したものだとか、どちらが本当かは知らない。)
体格が大きい者たちがこれを担がされた。
私は持ってみたことはないが38式と違わないように見えた。
「引鉄(ヒキガネ)の位置が前のほうなので担ぎづらい!」と扱った者たちが話していた。
このテッポーで撃てるタマはわが国にはなかった!
(s19/11-12)
昭和20年3月10日の夜明け前、東京方向上空一帯がその下の火に映えて一面まっ赤、
明けて黒雲の断崖にかわって更に上空に積乱雲に似た雲?煙? 益々恐ろしい風景だった。
別の空襲の夜「警戒配備―総員起床」、今度もまた呆然と待機しているのは無駄だと思ったので、
当直練習生の前で「哨戒電探配置ニツケ」と自ら称えてから特別勝手が利く半地下電探室へ走った。
富士山に向けてあったアンテナを180(ヒトヤーマル、真南)に回して、13号電探のスイッチを入れる。
ブラウン管が温まると突然画面に大編隊の梯団が次々に迫ってくる。
実習機なので報告不要だが、規則通りに呼称しながら記録する。 送信出力は半減で十分!
続々士官たちが寄ってきて左右と肩越しに5〜6名、後ろにもまだいる! 聞き覚えの声は無い。
予備士官と任官前の学生たちらしい! 皆、恐ろしい予感を抱いてスクリーンを覗き込んでいる。
操作は上等飛行兵ただ1人!
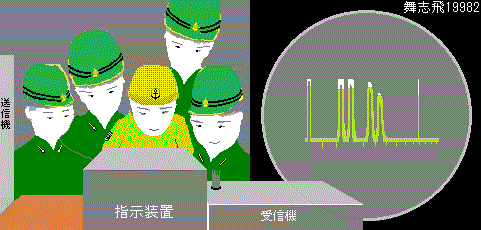
【この日は、戦後各種の資料とつき合わせて、4月13日だった】
実習機は代わる代わる大勢が扱う。狂わせたままになっていることが多い。命ぜられたわけではないが後輩どもが乱した跡を度々手直した。
この日 愛機は応えてくれた!
そして、私の方向指示に応えた伝令と操作は何れも数等級隔たった上位者だ、普段ならとんでもないこと!
その折角の方向調整も、受信感度が飽和していて20度位振っても変わらない。大雑把に真南あたりに戻してあとは放置。
測定するなら、受診感度をうんと絞らなければならないが、それをしない ∵ 第2、第3の後続群が接近する?
凹みや傷でボコボコになっても、或いはサイパンまで戻り着けない傷でも下からは見えないから戦果にならない。
無傷に見えて落伍するのがいる。高度を下げたら撃ち落とせるぞ! ところが、立ち直って高度を取り直した。また別のテッキは、
エンジンの1つが黒煙を引いてやった!と思っているうちに、白煙に代わり、それも消えて、元のコースを取り戻した、残念!
搭乗員を殺す気はないが 魔物のB29は残らず叩き落としたい!
惜しい〜 から振り! がっかり!!
そのうち、やっと撃墜したときは万歳を叫んだ! しかし、東京は燃えている!!

炊事、洗濯、洗面、入浴、1万人が必要な水を相模川の上流から開渠で引き込んであった。
後日知った!
これが現在の横須賀水道といって横須賀市に至る上水道で、元々海軍が軍港用として造った水道だということ。
海軍は自前の水路の上に電測学校を造ってその水を途中利用した。
当時そのようなことを聞いたと思うが、関心が無かったからか、うろ覚えだった。
洗面所兼洗濯場の横に木の櫓が組まれて、木のタンク つまり、でかい水桶(ミズオケ)が載せられていた。
タンクに蓋はあったか無かったか知らない。時々上で作業しているのを見たが何科の兵隊だったのかなあ?
常にいわれていた。 「茶が烹炊所にいつでも用意してあるから茶を飲め、生水を飲んではいけない」
・・・ 禁じられていてもその水を飲む。全体では誰かが腹痛になったかどうか知らないが、私も周りのものも無事だった。お茶といっても緑茶が煮出されて紅茶色になっていた。
厳冬のさなか水が冷たいので食器洗いに、お茶を使って主計兵に捕まっていた。何分隊の食卓番か知らないが、同期だ!
「横着者!俺たちはそのような為に茶を沸かしているのではない!」
「俺が運んだ薪で沸かした茶だろう!」と食い下がって喧嘩になりそうだ、
「主計科に逆らうたらあかん、マズいもん食わされると損や」となだめて
「悪うおました、すんまへん」と代わりに敬礼してサッサと食器を片付けさせて引っ張って帰った。我が相棒さすが。
先方、主計兵は、年齢も年功も上だが等級は先週からこっちが上だ。 (20/2)
引地川(ひきちがわ)を渡って、電測学校正門まで700メートル、正門から兵舎まで更に1キロ余り。
きれいな水を西の相模川から汲んで炊事・入浴・掃除・洗濯などで汚れた水を東の引地川に流していた。
(水洗でなかったからトイレの排水は流していない。)
当時の一同に代わって(僭越乍)この川に謝意を表する。
葛飾北斎の富嶽三十六景にありそうな風景です。
富士山を背景に形のいい松が生えています。その松の脇を牛に引かれた大きな荷車が通っています。
すばらしく美しい! のどかな光景です。
積荷は樽がいっぱい。その樽の中身は何でしょうか? 初めのうちは私たちも知りませんでした。
当ててみてください。
・・・正解は、
海軍少将電測学校長以下我々に至る 万に近い数の士卒一同、軍務の合間に生産した有機肥料が詰まっているのです。
ごく荒れた日のことは知りませんが毎日滞ることなく往復しているのが見られました。
傍目にはのどか でも大変な仕事です。もしも休んだらどうなったことでしょう?
牛かたさん、うし君ほんとうにご苦労さまでした。

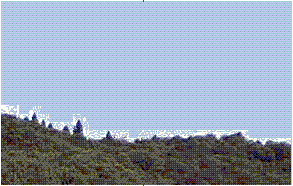
校内通路を単独行動中突然前方、丘の林の上に
F6F が超低空でこっちへ向かって現れた。「敵機〜」と叫んだ。
あたりの者がすばやく伏せた。持ち物を放り出したのもいた。みんな知らない分隊。
爆音が聞こえたのはぐんと大きく見えてからだった。私は頭上を通過する敵を見送った。
確実に私の真上。高度40、針路富士山の南、低空のまま。
10メートル程歩いたとき士官帽に捕まった。
「飛長!『敵機』と喚呼しながら突っ立っていた、なぜ伏せなかったか」
「敵機の腹が見えました。我々を攻撃すれば機首が下がります。あの位置から機首を下げたら地面に突っ込みます!」
「さすが甲飛だ、よし!」(直感! 間もなく任官する学生。細い棒を持ってあご紐をかけていた。)
そのとき私は真空管を収めた木箱を携行していた。
敵グラマンよりも箱の内容物に衝撃を与えるほうがコワかった!
グラマンの機銃に射抜かれたら 木口小平! 「シンデ モ シンクウカン ヲ ハナシマセンデシタ。」
「敵機の腹が見えました」とは、【敵パイロットの腹の内が読めた】ということではありません。
敵機の胴体の下部が見えたということです。それは腹に爆弾もロケットも抱えていないから、
「この位置への攻撃は不可能」との意味を言ったのです。報告を受けた甲板士官見習いが、
文系で、前者の意味に取ったかもしれない! ハハハ 間違ってくれてありがとう !!
付近から2人の様子を本物の甲板士官に見られている気配がしました。その気配を
遠目に感じて動作に節度をつけて彼の上官振りを損ねないよう気を使いました。
このような時、殊更舐めた態度をとる同僚もいましたが、私はしません。
(20/7)
敵艦載機は見慣れていたがこんな急なことは始めてだった。飛来の方向も、いつもと違う。
いつもは、4km真北の厚木海軍航空隊を空襲しようと頭上を通過する。
飛行場上空で翼やペラを日光に光らせながら波状攻撃しているのを度々見た。
青空に黒い点が現れて向かってくる!
基地から応戦した対空機銃弾が ソレて私等の辺りに空気を裂く音と一緒に降って来る。
「味方の弾だぞ 当たったら犬死だ! 早く(壕に)入れ!」 怒鳴られたり 怒鳴ったり!
例外的コースの通過機は はぐれて集結地点を探して飛行していたものと思う。多分弾倉はカラ!
勝手な想像 はぐれ グラマン
母艦を発進して編隊を組み、ベテランにに先導されて やってきて京浜軍需施設を攻撃した。
奮戦の末、僚機からはぐれて単機になってしまった。心細かっただろう!
弾は撃ち尽くしている。どうやって帰艦するか?
このような時のためにあらかじめ教えられていた、
「富士山を見つけろ その南麓に向かって飛べ 半島が接近したら方位180度に取って進め X浬で帰艦できる」
日本軍と違って無線電話での誘導帰還は可能だ!
【帰還ナビは、あの低空では30浬が限度だろう】
「ジャップに捕まらないようにできるだけ低空で飛べ」とのアドバイスもあったかもしれない。
あのような低空は、よほどあわてぎみになっていたに違いない 丸腰になっていたことでもあるし!
わが方にしてみれば、超低空では電探には捕えられないし、対空射撃もコース上の陣地がよほど迅速な情報を得て待ち構えていなければ間に合わない。
私の真上を無茶な低空で西に向かって飛び越していった。終戦の1か月くらい前のこと。
後に思うに・・ 富士山を見つけて彼は一目散!
気圧の単位にヘクトパスカルもミリバールも用いられなかった。
問題
海面上高度3000米及ビ5000米ニ於ケル気圧ハ凡ソ何程カ 下記中ヨリ示セ
(1)400粍Hg
(2)500 〃
(3)600 〃
(4)700 〃
(5)800 〃
正解→ 3000米 (2)、5000米 (1)
問題−2
海面上高度一万米ニ於ケル気圧ハ凡ソ何程カ
正解→ 200粍Hg
下士官、兵には上陸札というのが渡されていた。木片に墨で氏名が書いてある。外出札とも言った。これを外出するとき衛兵所に提出しなければて出て行けない。帰着したとき貰い受ける。誰が外出中であるか衛兵所で把握できるための仕組み。
練習生中は持たされなかった。単独の外出がないので不要なわけだ。卒業して講習員になったその日にこの木札を、「海軍にいるうちは艦船部隊でも陸上部隊でもどこに転勤しても兵曹長になるまではずーっと使うのだから大切にせよ!」と言って渡された。
この上陸札、本来の目的のほかの使われ方があった。物品借用の際の質草にするのである。その際、俺たちの上陸札で借りられるのはスコップ1〜2丁程度のものだが古参兵曹のそれを預けられて行くと、こんなものまで借りられるのかと思うような、運べるものなら何でも借りてこられる。価値は雲泥の差だ、そして俺たちのは白木だが先輩のそれはニスをかけたか?と思われるほどに古色がついて貫禄があった。
ほんとうの名前は知らない。カボック。海軍だけでしか食ったことが無い食品。
コンニャクに似ていたがコンニャクと違う。見た目がコンニャクのようだが粗い!
見た目同様 味もコンニャクと少し違う。不味くはない!
風味が独特だった。汁の味が染みて美味いときもある。
厚さが7mmくらいで大小の気泡がある。コンニャクにもたまに気泡があるが比べて、やたらに多い。海綿と違って大きい泡
ゲルであることには間違いないが、汁が熱いからエゴノリやオキュートの類ではない。
何回も食わされた。おれたち兵隊は「カボック」と呼んでいた。(カボックとは、天然素材のマットレス)
貯蔵してある粉末状の原材料から烹炊所でありあわせの道具で調理したものだろう。
考えてみれば甚だ重宝!湯に溶かして20倍にも増える。気泡が入ってもっと増える! 3000食もわけはい!
専用の設備を持たずに、大量処理では外道もやむなく、味も見た目も粗い感じのものになった!と追想している。
いくら考えても、コンニャク以外に同類はない。
いざというときに泡を食わないように、普段から泡を食わされ?!
以上は想像なので、事実をご存知の方がおられましたらお教えください。

召集兵らしいおっさん兵たちに交じって新兵の第11期普通科練習生も!(右から2人目)。 わが同期はいない。
背景に21号電探のアンテナが見える。実習機ではない、実戦機! (20/7)
昭和20年、雑草が生える頃だから終戦まで間がない頃だったでしょう。
年配の召集兵が除草や煉瓦積みをやっていました。
彼らの私たちに対する態度や言葉遣いは決して上級者に対するものではありませんでした。
坊や扱いです。それはそうでしょう等級は2つ上でも15から20も年下に接するのですから。
彼らは古い昔私たち以上の軍歴を体験しているのです。
そのなかに、源氏鶏太先生?・・・(残念ながら確かめようがない)
まじめな人もいました。
外出時海軍共済の休憩所に入って行ったらおっさん兵の1人が席を立って挙手の敬礼をするのです。
答礼というものを始めてしました。
多分私くらいの息子のいるお父さんなのだろうな! (20/6)
 『破編』に書いたが、11K指示装置の拡大鏡を外してタバコライターに使ったその下士官は、太陽の出ていないときは給電線を鉛筆の心で短絡させてタバコに火をつけていた。6センチ程の鉛筆の両端を削って常に携行している。短絡させるとチチーと音がして心の先から火が出る。うまく付かないときは、赤鉛筆を添えると炎があがる とか?(私の見た限りでは成功例なし!)その『落第ボタ』から習うべきものは全く無い。 反面教師という言葉は未だ無かった!
『破編』に書いたが、11K指示装置の拡大鏡を外してタバコライターに使ったその下士官は、太陽の出ていないときは給電線を鉛筆の心で短絡させてタバコに火をつけていた。6センチ程の鉛筆の両端を削って常に携行している。短絡させるとチチーと音がして心の先から火が出る。うまく付かないときは、赤鉛筆を添えると炎があがる とか?(私の見た限りでは成功例なし!)その『落第ボタ』から習うべきものは全く無い。 反面教師という言葉は未だ無かった!
指導する下士官がそんなだから、練習生に洗濯物を送信機に懸けて乾かす奴が現れる。すぐ乾く! 私はそのような靴下や褌を兵器に懸けるようなけしからん事はしなかった。 自生のユリの球根を掘ってきて送信管T−311のそばにおいて置く。 交代時間の前に取り出す。 焼けてはいないけれども、生(なま)でもない。一ひらずつ戦友と分けて食ったときは、うまかった。
(20/5)
海軍に「さチン」「よこチン」「まいチン」「くれチン」と4っつの分類があった。
この4っつのそれぞれに次の4っつの、どれかが対応する。
「はしっこい」「おひとよし」「せこい」「でれすけ」
海軍経験者ならばどれとどれが当てはまるか分かるはず。
多少の例外はあるが、特に新兵は、はっきりと、らしい形になっている。
激しく鍛えられると中には極端から極端に逆転するものがいる。
「でれすけ」と思われていた者が「はしっこく」なったり
「おひとよし」が、「せこく」なったり、
その逆もある。ま、そんなのは一時的で、
やがて、たいていは平均化して偏りが目立たなくなってくる。
平均化しながら、ひとつの方向へ『引っ張って』行かれる
いや、『引っ張って』というよりも、『追い立てられて』か・・・
そして、一等兵、上等兵へと進んで海軍軍人の型が出来るのである。
背筋が伸びていてカッコイイ とは「海軍士官らしいかたち」で通っているが、
古い下士官には、「背筋を伸ばせ」と兵たちを鍛えながら、自らは、なぜか
ちりけから、うなじにかけて前傾して頭部が前に出ているのが目立つ。
そのわけを、俺たち新兵を威嚇しているうちに、そのポーズが身について
直らなくなってしまった「型」だと私は、思った。 「屈辱の海軍電測下士官兵」
直接聞くのは恐れ多いので、その型になっていない例外の先輩になぜかを
聞いて見た。「頭上に配管やバルブがある狭い艦内で、頭を打たないように
通行している習慣が、そのような体形を作ったのだ」とか。 !?!?
兵曹長と予備学生は同じ階級章をつけて同じ軍服を着ていた。
それでも誰が見ても区別が付く。一目瞭然!
軍歴の違いが挙動や姿に出ている。
ところが、何百人かに1人くらいは兵曹長と間違われる学生、
学生と間違われる兵曹長がいた。
こういう方は両者とも特別の偉い何かを持っておられて敬服すべき上官だった。
「たんつぼ」というものがあった。鉄道の客車の中にも付いていた。
海軍では各班に1個ずつ備えられていた。私の班では、全く使われた跡がなかった。教班長室のこれは、酔っ払った下士官がへどを吐くために役立っていた。
痰壷当番は、ゆすいで磨いてクレゾール石鹸液を入れ、半分チョイ下まで水を足して据付ける。使っても使わなくとも毎日これを繰り返していた。
無駄な決まりだと思った。勝っていた頃は真鍮製らしいが、私らの頃は白い陶器だった。
戦後、某ペットの霊所で犬や猫の骨壷を見たら痰壷を思い出した。フタだけ違って本体はそっくりそのものだ!
海軍でフネに慣れない兵隊が反吐(へど)を吐くのに必要だった。そのために出来た規則を陸上部隊にも広げたのだろう。聞いてみたら、やはり
陸軍にはなかったそうだ。
< 大先輩の著書拝読中、気付いたので以下に書き加えます。> 【 回顧 海軍十年 深田正雄 】246ページ『四 旧型艦の修理、改造』のうちから、
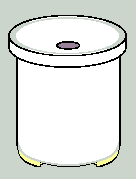 『煙突は高く、黒煙を濛々と吐いて走る姿は他の艦から見ると勇壮そのものだったが、風向きによっては上甲板に燃えカスが雨のように降ってきて眼も口も開けていられなかった。』
『煙突は高く、黒煙を濛々と吐いて走る姿は他の艦から見ると勇壮そのものだったが、風向きによっては上甲板に燃えカスが雨のように降ってきて眼も口も開けていられなかった。』
共通点! 鉄道もSL時代は、石炭を焚いて走った。
この共通の原因が海軍と鉄道の両者に痰壺を必要にさせたのだ!
船酔い、乗り物酔いも原因だが、この原因の方が大きかったに違いない!
煙は常に周辺を流れている。そして、ときたま居住区・客室へ ボワ〜ッ と吹き込んでくる。
この煙が気管や肺を刺激して痰がでる。
訓練・教育のためか伝統維持のためか、煙とは縁のない陸上部隊の兵舎にまで供えられていた。
石炭を焚かなくなってからも習慣が続けられていた!
これが海軍にあったわけだ、陸軍には不要!
鉄道のものはGHQにむりやり短期間に外させられた。
| 例 | 呼称 | 振動方向 | 波動形態 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 電波 | 水平偏波 | 横に振動する | 『横波』 | |
| 電波 | 垂直偏波 | 上下に振動する | 『横波』 | |
| 電波 | 円偏波 | ぐるぐる回る | 『横波』 | |
| 音波 | 前後に振動する | 『縦波』 | ||
| 水面の波 | 表面波 | 『トロコイド波』 | 『縦波』+『横波』 |
『縦波』『横波』の説明は他のHPに解り易いのがいくつもあるので省略する。
舟を転覆させるのは違う意味の『横波』(よこなみ)。
地震の伝わりは縦波と横波が主だが、それは家の縦揺れ横揺れとは別!
地震には表面波もある。 頭の中がごちゃごちゃしましたか?
「快刀乱麻を断つ」 “それっきり”になる! いいんですか?
一筋ずつほぐせ!
生きる ・・・・ 物も心も。 快刀が乱麻を断てば 燃えるごみ
海軍から手旗信号やモールス信号など役に立たない技を持ち帰った。
残念なのは『結索』をおき忘れてきたことだ、これを忘れてこなかったら、どれほど役に立ったことか・・・
『結索』とはロープをクルクル絡げるワザである。この技を使うと
引くとき、吊るとき、縛るときなど、簡単で、しっかり! キッチリ!
そして、用が済んだとき ほどき 易い。
羅針儀、六分儀、測距儀そのほかまだある。海軍では機器に「儀」の字をつけるのが好きだった?
羅針儀、測距儀などは陸軍にも同様のものがあったが「儀」の字のつかない別の呼称をしていたようだ。
電波探信儀も然り。
優秀だったと聞かされた9期普電測(第九期普通科電測練習生)は、私らが入隊した頃に卒業した。
10期普電測が一緒にいたが一足早く卒業。同じころ乙飛電測も卒業した。
11期普電測や2期甲飛電測は土工など荒仕事に駆りだされて電測を習う暇はなかったようだ。
最後のころに特別幹部練習生が入隊してきた。そのほかに高等科練習生がいたがよくは知らない。
予備学生、予備生徒のことはなおさら知らない。時々遠目に見えていた存在。学生と甲飛は
広い構内の端と端に置かれた。学生が将来上官になった時に不都合がないよう、訓練の様子
を覗かせない配慮なのだろう。
私たち1期甲飛電測が一番大勢だった。
いつの日か所属する隊の本部に1〜2名 正規の候補生が来た。短剣は別にしても、俺たちと 七ツ釦
は同じようでもどこかがちがう。生地か、仕立てか、着こなしか、それを3年も余計に着て
いればシマる訳だ。1週間もいたかな。 教えに来たのか? 教わりに来たのか?
あ!そうでしたか やっぱり! 彼らのは麻で俺たちのは綿、差をつけられたものだ!
電波兵器に偉い軍人が好む【威風堂々】などは存在しない。電波兵器とはそういうもの!
14号電探は見たこと無いが、これもでかいだけと思う。
そういう中で12号電探はちょっとだけれども見栄えがした。
12号電探の実働機を見学、そこで勤務していた下士官は12号を礼賛していた。
11号・13号は欠点だらけのように言う。
13号を最高のものと教えられている私たちは、新たな見方を誘われた。
外観、室の内外、機器の輪郭などすべてが実働機はキチンとしていて、感じとして定規で描い
たように整然としていた、比較して13号の電探室内外は、フリーハンドで描いたような感じ。
同じ12号の実習機に比べても配線は整理されているし、壁や床は磨かれて光っていた。
感度がよい! 実習機の12号や13号では感じない大島、三浦半島、房総半島も映っていた。
最適な場所が選ばれていたからに違いない。椅子も工作科製と違って軟らかに座れる本もの。
教官・教員たちは13号電探の良い点だけを教えることになっていたのだろうか?
実働配置の先輩たちはそのような制約がないからだろう、思ったとおりを聞かせてくれた。
「13号なんかおもちゃだ」とも言っていた。
確かに、12号電探は姿が美しくその点名器だった。・・21号(艦船につけたもの)は
容姿不評だったそうだが・・
今で言う電子機械、嘗ては真空管が使われていた。
機器の性能が落ちてきたなと、感じたらどの真空管の寿命が尽きたのかを判断して取り替える。
真空管の寿命は ばらばらなので、数が多いと完全状態の保持に苦労する。
現在では乾電池以外の部品は機器本体の寿命より長いので部品に[寿命が存在する]など考え
ない。しかし陳腐化が早いので、機器〜設備まるごと消耗品だ。
昔は兵隊が自虐自嘲「俺たちは消耗品だ」と言った。兵隊に限らず企業の従業員は消耗品だ。
[耐用命数三十数年!]
時勢変わって今や部・課・工場、いや、会社まるごと 消耗品!
甲種飛行予科練習生として入隊したため、派遣という名目で電測学校に入校したけれども一般の
兵隊よりも進級が速い。何彼について妬まれの対象になった。
先ず第1に、「しごかれなくて進級すればヤワな兵隊になる。お前ら進級が速いのだからうんと
しごいてやる」と、暇なししごきを受けた。
第2以下省略。
他の兵種から見ると特急速度で兵長になったが、そのころになると、1人1人に妬まれ防衛策が
身についてくる。数の中には、
ここまで何年もかかってようやくなった上等兵を前にして「お前らは・・・」と、上からものを
言える器量の持ち主もいた。
また、
何を言われても鈍感に徹底してしまうとか、ブツブツこぼして発散させる等の姿勢屈服は潔く
(いさぎよく)ない。
私には1つの方策が身についた。
教官、教員に常習的に追及質問する。いわば揚げ足取りをする。自己満足だだったろうが、晴れ
がましく効果大。 このための学習努力は惜しまない!
たまには、逆効果もあるので相手の見極めと手加減必要。これも習得。
わずらわしい 陰の仕返し などはなかった。
初対面には利かないので3〜4回は忍耐。
その妬まれ兵隊の甲種予科練にも妬む相手ができた。
戦争が大きくなると大量に兵員が必要になって、等級のインフレーションが起きる。
更に、進級が速い制度を作って募集する。
今まで不適格とした近眼、色弱、胸囲不足などに残っている優秀者が探された。
彼らに課された採用試験は高度だった。
同じ七つ釦の兵長でもすぐわかる。
あみだかぶりで、歩き姿がしまらない、半数くらいは眼鏡をかけている。
負け戦だからではない、勝った 敵サン にも同じような兵隊がいたらしい!
電波探信儀の性能とは、
第1に、目標を如何に遠距離から探知できるか、如何に精密に測定できるか、
第2に、故障が少なく取り扱いが便利か
だが、後者のほうがより重要な性能項目である。
米英と比較して特に劣っていたのは後者の方であった。
海軍が我々電測兵を大量に養成した狙いはこの後者の弱点を人的に補おうとしたと推測
する。即ち、
故障修理を迅速に行うことを第1の目標として、それだけではなく更に、
機械がやるべきところをモーターや歯車に代えて人力を投入し、
伝令と称して通信回線に代えて大声を順次中継する。
俺たちが称えられた『敵に劣らない優秀な電測兵』とは観測技量だけでなく
修理や機械の代役がこなせ、正確に情報伝達ができることだった。
畢竟すれば、
材料だった我々が電探の部品として完成。レッテルである普通科電測術章![]()
が貼られて出荷された、それが卒業式だ。
思い出した! もう1つ追加しておきたい。
13号電探は受信帯域幅が限度一杯にまで狭められた。【 11号、12号、11Kは 5倍の余裕があった。】
受信感度を向上させるためだが、温度など環境変化の影響を受けるので安定度が損なわれる。
その失った安定度は我々電測兵が追跡して補うのである。
 特に親しい親友とか朋友というものは自然に醸成されて出来るものである。
特に親しい親友とか朋友というものは自然に醸成されて出来るものである。
その親友である戦友が上官の命令で強制的に作られる!
今の人には理解しがたかろうが夫婦でさえ本人の意向は関係なしに結ばされた時代であった。
部隊が新しく編成されると最小単位の班ごとに身長順に横2列に並ばされる。
前後に組んだ2人は『相番号』といって互いの個人的なすべてを知り合わなければならない。
出身が全国的なので方言の障壁も克服する。
もちろん生なましい人間性も熟知して
それより後は一本の
煙草も二人わけてのみ
ついた手紙も見せ合て
身の上ばなしくり返し
肩をだいては口ぐせに
どうせ命は無いものよ
死んだら骨を頼むぞと
言ひかはしたる二人仲。
の
戦友が出来上るのである。
編成替えもあったがいつも『相番号』が嫌な奴でなくてよかった!
東北出身と九州男児! 両極端の戦友が65年未だに続いている。
相手が呉鎮だったらこうは続いてはいかなかった!
火縄の火がぷらぷら揺れている
真っ暗闇で煙草を吸う顔は見慣れている筈なのに判別できない。
口先から煙草の火が照らして異様な面相、まるで化け物だ!
声を聞けば誰であるかわかる。黙っている奴はわからない。
電測学校入校時、私たち3000人が居住する区画は未完成で、兵舎はどうやら間に合った格好でした が、
10棟ある兵舎の周囲は桑畑のままで、入隊式前日の私たちが、切り株にワイヤーロープを縛り付けて
人海戦術で引き抜き、そのあとを裸足の「その場駆け足」で踏み固めました。
兵舎内の通路も私たち全員の踵で三和土(たたき)に仕上げました。
烹炊所(厨房)、厠(トイレ)、洗面・洗濯場は間に合っていましたが、管理棟や講堂(教室)は建築中でした。
浴場は未だなので、はるばる別な兵舎群までの「もらい湯」が ずっと後まで続きました。
終戦の何年か後、訪ねたことがありました。一面麦畑、 まだ自動車工場が出来る前。
桑畑 → 海軍電測学校 → 麦畑 → いすゞ自動車工場 (神奈川県藤沢市)

にし
まさに多忙な新兵教育のころで風景を眺める余裕などありませんでしたが、寒風に吹かれながら厳しい訓練の合間に仰いだ富士山が思い出されます。地元で毎日見ている人たちには感じられないと思いますが、故郷を離れて来ている私たちは富士山を仰ぎ見て、いい眺め、美しい、清々しい、雄大・・・・
ところで、富士山の手前に「おおやま」という山が見えていたのを思い出せますか?私はずっと忘れていました。富士山を背景に見事な松があったのは覚えていますが、大山は忘れていました。富士山が特別に大きかったからです。
戦後40年程のある日、家族の用事で神奈川県の七沢に行きました。町を外れて近くに山が現れたとき突然「おおやま」と叫びました。更に同乗の家族に「あれは大山という山だ」と言って訝しがられました。なぜ、はじめて見た山の名前がわかったのだろうかと私自身も家族も不思議でした。理詰めに過去を追って、訳を知るのに暫くの時を要しました。初対面じゃなかったのです! それにしてもすっかり消えていた記憶が突然燃え上がったのには驚きでした。
電測学校で電探を実習していたとき、調整のためにアンテナを富士山に向けます。ダメな電探には富士山が映らない。が、それでも大山は近いのでちらっとでも映れば手掛かりです。大山の反射像を頼りに整備して、やがて富士山が映れば調整成功。そんな時に苦慮しながら眺めた大山の形と名前の記憶が奥の奥に圧縮されて収まっていたのでした。
今地図を見て調べると電測学校からの距離が富士山は大山の約3倍、頂の高さも富士山は大山の約3倍だから両方の仰角はほとんど同じです!【地球接線下に富士山が7.5%沈下するのを見込む】
電波の反射率が同じとしたら、反射波の強さは距離の4乗に半比例して81分の1で、富士山が19デシベル低い。
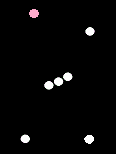
ひがし
巡検前に号令演習がありました。各自思い思いの方に向かって吼える、怒鳴る、囁く、自分の故郷の方を向いているいる者が多かったと思うけれども私は東の向かって叫んでおりました。
東の空にオリオン星座の三ツ星が縦に並んで昇っていました。その輝きに正対しているのです。美しいと思いました。そして、毎晩同じ時刻ですのに東の星たちが少しずつ高くなっているのに気付きました。号令を叫んでいる私を励ましながら見守ってくれているように見えました。
やがて初年兵教育が終り号令演習は無くなりましたが、晴れている限り必ず三ツ星を仰いでおりました。夜、厠から帰って寝具に入るとき大抵のものが「不寝番 今何時だ」と聞きます。寝られる時間が残り少ないとがっかりしたものでした。私は三ツ星の位置から時刻がわかったので不寝番を呼ぶことはありませんでした。
その三ツ星がだんだん東から南、そして西へ回って卒業の頃には見られなくなってしまいました。
それから4か月 復員途中便乗の無蓋車から未明の、行く手の空に号令演習のときと同じ形に三ツ星が昇っておりました。
迎えてくれたのか、ありがとう 三ッ星は列車が東に向かっていると知らせている、柏崎だ。漸く家は近い!
守護神のように感じました。そうだった!祖母が三ツ星「さま」と言っていた!
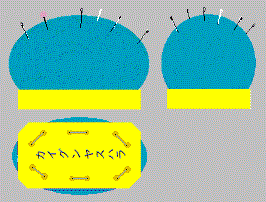
「針坊主」を辞書『大辞林』で引いたが載っていない。そこで、その辞典で「針刺し」を引いたら『裁縫用の針を刺しておくための道具。さびないように、髪の毛・ぬかなどを布で包んで作る。針立て。針山。』とあった。一般的ではないと思うがここでは母が言っていた「針坊主」とする。
甲種飛行予科練習生に入隊するときに母から、母自らの髪の毛を切って布で覆って長方形の板切れに取り付けた針坊主を作って様々の針を数本刺して持って行けと渡された。母の思いが籠っている、お守りである!
思いもかけなかったことだったが、軍隊生活で針仕事は多かった。当時女子は家庭でも学校でも裁縫を習っていたが男子は母の仕事を見ていただけだから、無器用なことしかできなかった。不細工でもほとんど毎日やらないわけにいかなかった。
母が作ってくれた針坊主が重宝した。そのうちに隣の班の戦友が「見せろ」と言うので貸したらそっくり同じものを作った。髪の毛は兵舎周辺には無いはずだから何を詰めたか知らない。そのうちに分隊中に一見全く同じものがいくつか作られて役立っていた。それぞれ くに の おふくろ に髪の毛を送らせたのだろうか?
海軍の「41号電波探信儀」は対空射撃用電探で、対空哨戒の我々には専門外の精密距離測定の機能があり、その重要部品を見せられた。電気抵抗の針金を巻いた紡錘形だが片面にだけタップが出ていたので針坊主に似ていた! ( 11 taps * 500 Ω @ 5000 Ω ) 精密距離測定方法3種類中の第2番目
戦争が終わって「針坊主」を持ち帰って、独身時代が終わるまで使っていた。母が「自分が作って与えたものを大事に使っているな」と思ったのだろう手に取って裏を見て「カイグンヤスハラ」と墨書してあるので「大それた書き方をしたものだ! 見つかって上官に咎められなかったかい」と言うから「何回も別々の上官に見つかったけど誰も冷やかしだけでお叱りは1回もなかったよ」と答えた。持ち物点検でも名前が書いてあるとして「ヨシ!」とされた。
今も物置の棚の奥にある筈だ。
昭和20年8月15日
ようやく涙が乾いて日が暮れた。気がつくと夜景が出現していた。
忘れていた!
今朝までは広漠とした廃墟のような暗闇だったのが、今夜は明るい街が現れた!
夜景に思えたのは灯火管制が解除された兵舎の窓明かりだ。
2階建ての本部館などは豪華なビルに見えた。
いずれも何十ワットかの白熱電灯でしかないのだが、
先程とはべつの涙で潤んでその明かりがキラキラ繋がって華やかに見える。
こんな景色何年ぶりだろう。感激とはこの涙のこと!
昨晩までは、軍も工場も民家も明かりを外に漏らさない。
勿論警戒警報、空襲警報がかかれば、外面は厳重に真っ暗だが普段でも暗い。
物も人も黒く星あかり月明かりに陰が見えるだけだった。
大勢地べたに尻をついて夕涼み。これも昨夜までは絶対に許されない光景!
忘れてはいないが 思い出したくなかった。
俺たち同期の出版物『甲飛電測二飛曹』前後両編を見たが誰も書いていない。誰も同じ気持だったか?!
いろいろ書いてこれだけ外したのでは片手落ちだ!
これを外しては死んだ戦友に済まない! 数字までは知らないが何人か失っている。何人くらいだろう?
隣接分隊の範囲では病死者があれば知れるがそれより離れた分隊のことは知らされない。
噂になって聞こえて来るだけ。
兵舎ごと隔離されたから、ここもか!と患者が出たのがわかる。
敵よりも恐ろしい。
第202分隊の山下上等飛行兵の通夜に列席した。山下のお父さんに挨拶を受けた。
骨箱に 写真も、供えられている品々は、蝋燭の灯だけなので暗くてよくわからなかった。
その建物は祭壇専用だ。傍を通ってもそれまでは気付かなかった。兵舎か講堂だと思っていた。
翌朝には悲しみを忘れろと命令を受けた。
山下の分隊は隔離中だったからだろう、通夜は隣分隊の俺たちが手伝ったわけ。
通夜の参列者は屍衛兵と呼ばれた。衛兵としての責務があったのかは忘れた。
「通夜」と言えば私用だから「屍衛兵」と称して時間を与えられたのかも ?
体操が終わると首が痛い者がいないか調べられた。感染者が発見できるとか?
この流行性脳脊髄膜炎は春先だけで暖かくなると流行は止んだ。
私の所属した第201分隊に感染者はなかった。
この病気で同期3000名中10名近くも死んだのではなかったか?
伝染病ではない。死亡者の有無は知らないが「全身衰弱」の患者が多数いた。
軽いものから順に、休業、入室、入院の別があった。
休業とは、体力を使わない課業にだけに参加して「かったいぼう」と呼ばれていた。
娑婆の「脚気」と海軍の「全身衰弱」と戦後の「栄養失調」は同じ病気に思う。医者はどう言うか?
下肢が膨らんでアキレス腱が見えなくなる。掴むと指の跡がしばらく消えない。
当人の苦しみを知らないが同情もした。世話も焼いた。同じ麦飯を食って同じく動いて
体力があっても罹る? 注射が効いてすぐ治る者、幾日も病室から帰って来ない者 さまざま。
長く休んだ者は日数不足で次期回しになった。何名かづつに別けて後輩各分隊へ移された。(次期回し、留年でない、2期/年だから)